「名張毒ぶどう酒事件」解明のカギ握る新証拠と2時間の空白
検察が軽視する空白の時間
会長宅にブドウ酒が届いたのが午後3時前後であれば、奥西が公民館に運ぶまでに少なくとも2時間以上の空白が生じ、事件は全く異質の構図を示す可能性がある。
ところが懇親会参加者など事件に関わった住民たちの供述は奥西の逮捕後、起訴5日前の4月19日を境に一斉に変転する。
「(売ったのが)4時をすぎていたのではないかと言われれば、あるいはそうではないかと思う。確かなことは昼ご飯と夕ご飯の間ということ」(酒店の女性)、「会長宅に届けたのは4時半から5時の間違いだった」(A氏)――。
「2時半から3時」というはっきりした記憶が、わずか20日余りのうちに「昼ご飯と夕ご飯の間」にまでぼやけてしまうのは尋常ではない。A氏のメモも一体何だったのか。
唐突な変更の理由について当事者たちは「思い違い」「(当初は)時間の観念がなかった」と言葉を濁すばかりで、合理的な説明は今に至るまでない。
ちなみにA氏は件のブドウ酒瓶王冠の歯型に関しても事件発生直後、宴会の席で自分が王冠を歯で開けたとかなり具体的な供述をしていたが、ほぼ同時期にこの証言も「はっきり記憶がない」と撤回している。
津地裁の無罪判決は、示し合わせたかのような供述の一斉変更を「かかる時刻の訂正は検察官の並々ならぬ努力の所産」と痛烈に皮肉り「このことは各該当の報告書を一読すれば容易に理解し得るところである」と断罪したが、以後これら供述変転の不自然さは直視されることなく、今に至るも事件の構図を理不尽に縛り、一人の男に死後まで死刑囚の汚名を背負わせ続けている。
5人の命が奪われた春の夜の惨劇から間もなく65年。司法が迷走に次ぐ迷走を重ねる中で、あまりにも長い時間が失われた。奥西のほか、すでに鬼籍に入った事件関係者も多く、現場となった公民館も既にない。
刑事訴訟法では、当事者が死亡した場合の再審請求が可能なのは「配偶者、直系の親族、兄弟姉妹」に限られる。奥西の親族で唯一、その意思を持つとされる妹は現在95歳。残された時間が刻々と減る中、「裁判で無罪を証明する」と決して恩赦を求めようとしなかった奥西の無念が晴らされる瞬間は果たして訪れるのだろうか。
(一部敬称略)
取材・文/岡本萬尋
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝
2024.10.20 芸能 -

吉岡里帆が33歳誕生日に「意味深宣言」! ガチ濡れ場開戦でポスト広末へ
2026.02.14 芸能 -

大原麗子さんと父親の確執「絶対に離婚はしませんから」渡瀬恒彦さんとの結婚時に宣言も…【週刊実話お宝記事発掘 昭和56年12月24・31日合併号掲載】
2024.08.18 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

玉の輿の幸せが暗転! 20年ぶり再会実母の「たかり」に困惑する33歳資産家妻の悲劇
2026.02.15 -

谷原章介がギャラ大幅減でフジテレビ残留?春の番組改編は「聖域なきリストラ」の嵐
2026.02.15 芸能 -
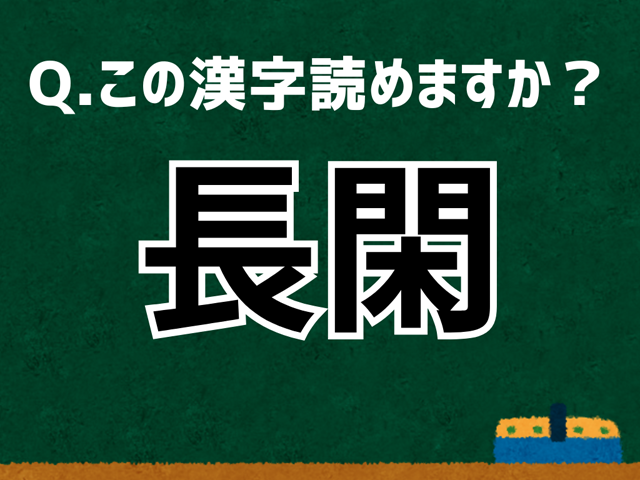
「長閑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.14 エンタメ -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり
2026.02.14 芸能 -
アイドル、踊り子、セクシー女優…小向美奈子が歩んだ波乱の四半世紀
2026.02.14 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝
2024.10.20 芸能 -

吉岡里帆が33歳誕生日に「意味深宣言」! ガチ濡れ場開戦でポスト広末へ
2026.02.14 芸能 -

大原麗子さんと父親の確執「絶対に離婚はしませんから」渡瀬恒彦さんとの結婚時に宣言も…【週刊実話お宝記事発掘 昭和56年12月24・31日合併号掲載】
2024.08.18 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

玉の輿の幸せが暗転! 20年ぶり再会実母の「たかり」に困惑する33歳資産家妻の悲劇
2026.02.15 -

谷原章介がギャラ大幅減でフジテレビ残留?春の番組改編は「聖域なきリストラ」の嵐
2026.02.15 芸能 -
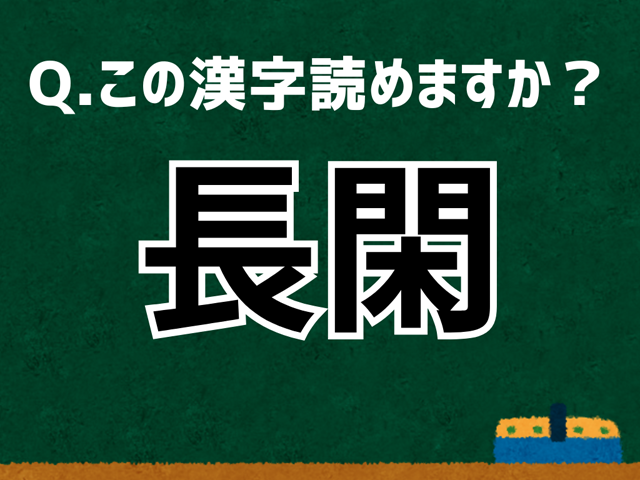
「長閑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.14 エンタメ -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり
2026.02.14 芸能 -
アイドル、踊り子、セクシー女優…小向美奈子が歩んだ波乱の四半世紀
2026.02.14 芸能

