阪神球団史上最悪の暴虎事件「横浜スタジアム審判集団暴行事件」はなぜ起きたのか?
2025.05.28
スポーツ

阪神球団創設90周年。プロ野球界で長らく巨人と人気を二分してきた“西の雄”だ。その阪神の番記者として陰に陽に取材してきたのが、元スポーツニッポンの吉見健明氏。トップ屋記者として活躍した同氏が、知られざる阪神ベンチ裏事件簿の“取材メモ”を初公開する。
1982年8月31日に起きた『横浜スタジアム審判集団暴行事件』
現代のプロ野球は子供も安心して楽しめる興行となり、すっかり乱闘も見かけなくなった。
ただ、オールドファンにとって、乱闘は選手のむき出しの闘争心や意外な人間性を垣間見ることができる密かな楽しみだった。
昭和の球場は今より人間臭い場所だったのだ。
阪神の長い歴史の中で、乱闘といえば、真っ先に思い出される事件がある。
1982年8月31日に起きた『横浜スタジアム審判集団暴行事件』だ。
対横浜大洋ホエールズ戦、1対1の同点で迎えた7回表、阪神の攻撃。藤田平の打球が三塁ライン際のフライとなり、三塁手・石橋貢のグラブをかすめて、ファールゾーンに転がった。
三塁塁審・鷲谷亘の判定はファール。これを見た三塁コーチボックスにいた河野旭輝が「石橋のグラブに当たっていた。ファールではなくフェアだ」と猛抗議を開始した。
その瞬間、阪神の一塁ベンチから島野育夫、柴田猛の両コーチが鬼の形相で飛び出した。
それからはあっという間の出来事だった。島野、柴田に監督の安藤統男も加わって鷲谷審判に詰め寄る中で、島野がヒートアップ。
鷲谷審判に殴る蹴るの暴行が始まり、後方からは柴田の蹴りと鉄拳も飛び出し、鷲谷審判が地べたに倒れ込んだのである。
駆け付けた審判団や両チームの選手たちが2人を引き離そうとするが、止まらない。今度は2人に退場宣告をした主審・岡田功の右わき腹に柴田のパンチがメリ込み、よろけるようにグラウンドに膝をついた。
球場は大混乱となり、責任審判の岡田は怒りのあまりプロテクターを地面に叩きつけ、審判団を全員引き揚げさせてしまった。
そのまま没収試合になる可能性もあったが、島野・柴田が退場となり、安藤が審判室を訪れて謝罪することで試合は再開した。
これが阪神球団史上最悪の「暴虎事件」である。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -
長濱ねる、齊藤京子、平手友梨奈…欅坂系列グループOGのソロ活動に明暗クッキリ
2024.10.23 芸能 -
芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機
2026.02.12 芸能 -
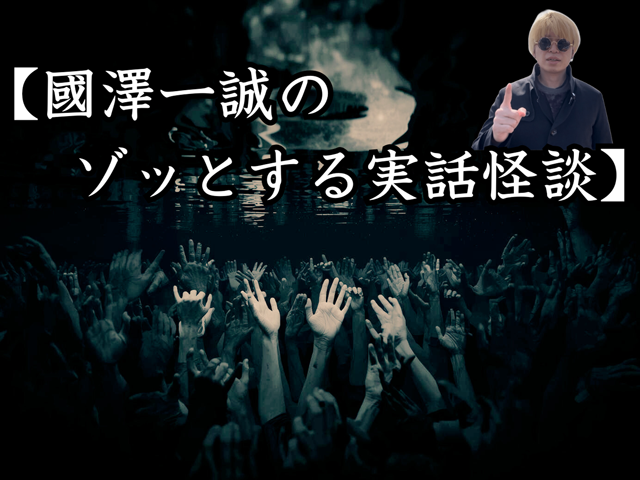
【國澤一誠のゾッとする実話怪談】第二夜 生放送に映り込んだ“死を予言する女”――新宿アルタ前で目撃された緑のワンピースの怪異
2026.01.26 エンタメ -

【異常な幕引き】国分太一、日テレへの“平伏謝罪”に漂う“強烈な違和感” 「何への謝罪か」と批判集中
2026.02.12 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

「政治を科学する男」はなぜつまずいたのか? 鳩山由紀夫の異色すぎるリーダーシップ
2026.02.12 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -
長濱ねる、齊藤京子、平手友梨奈…欅坂系列グループOGのソロ活動に明暗クッキリ
2024.10.23 芸能 -
芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機
2026.02.12 芸能 -
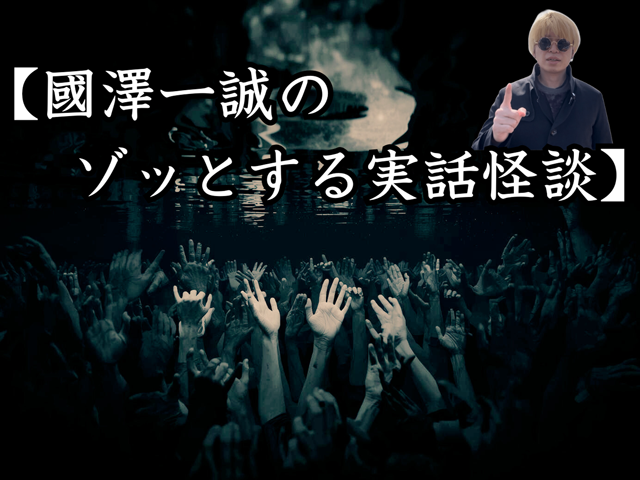
【國澤一誠のゾッとする実話怪談】第二夜 生放送に映り込んだ“死を予言する女”――新宿アルタ前で目撃された緑のワンピースの怪異
2026.01.26 エンタメ -

【異常な幕引き】国分太一、日テレへの“平伏謝罪”に漂う“強烈な違和感” 「何への謝罪か」と批判集中
2026.02.12 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

「政治を科学する男」はなぜつまずいたのか? 鳩山由紀夫の異色すぎるリーダーシップ
2026.02.12 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能

