東日本大震災の震源・日本海溝が再始動…高まる「首都直下地震」「南海トラフ巨大地震」発生の可能性
2025.03.12

日本海溝に潜り込む陸側の北米プレートが西に移動し、ひずみが徐々にではあるがたまり始めているからだ。
【関連】【2025年の大予言】平成の奇書『私が見た未来』が予言する2025年7月の「大災難」とは何か? ほか
さらに、千葉県東方沖の日本海溝には東日本大震災の割れ残りが存在するため、今では遠からず巨大地震が起こる可能性さえ指摘されているのだ。
事実、東北大の日野亮太教授はこう語る。
「(日本海溝の)プレートが次の地震の準備を始めているような動きをしている」
また、サイエンスライターは次のように指摘している。
「陸側のプレートにひずみがたまって、それを解放するときに地震は起こります。その意味では次の巨大地震が起きるのは、まだ数十年先の話です。ただ日本海溝の北と南には割れ残りの部分があり、それが動く可能性もある。これが怖いんです」
東日本大震災で破壊された断層は、岩手県南部から茨城県沖北部まで500キロ以上に及んでいるが、その南の端の割れ残りが動くと、関東地方に甚大な影響を及ぼす可能性があるのだ。
「千葉県が2016年に発表した被害想定によると、この割れ残りが動いた場合、最大でM(マグニチュード)8.2の地震になるそうです。最大8.8メートルの津波が銚子市を襲い、建物の全壊は約2900棟、半壊が約6700棟。死者は最大約5600人も出ると想定されているのです」(同)
実際、千葉県東方沖では1677年にも津波を伴う巨大地震が発生している。
「千葉から茨城沖には、数百年に1回のペースで巨大地震が発生し、津波が押し寄せていた可能性がある。千葉県匝瑳市と山武市で採掘調査を行った結果、海で生息する有孔虫の化石が含まれている砂の層が発見されたそうです。砂は当時の地表面を削りながら堆積していたため、津波で陸上に運ばれたとみられているのです」(同)
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

開幕前に解任確定!? 生みの親・原辰徳氏にまで見限られた巨人・阿部監督の“四面楚歌”
2026.01.10 スポーツ -
秋元康の大ブレイクのきっかけとなった“冬の昭和歌謡” 菊池桃子『雪にかいたLOVE LETTER』
2026.01.11 エンタメ -

山口智子、ガムテープと手錠を持った暴漢2人が自宅に突撃〜女性芸能人暴行事件史④
2021.12.30 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -

「自信があるから産んだんです」略奪愛も辞さなかった恋多き女優・萬田久子の覚悟と代償
2024.11.10 芸能 -
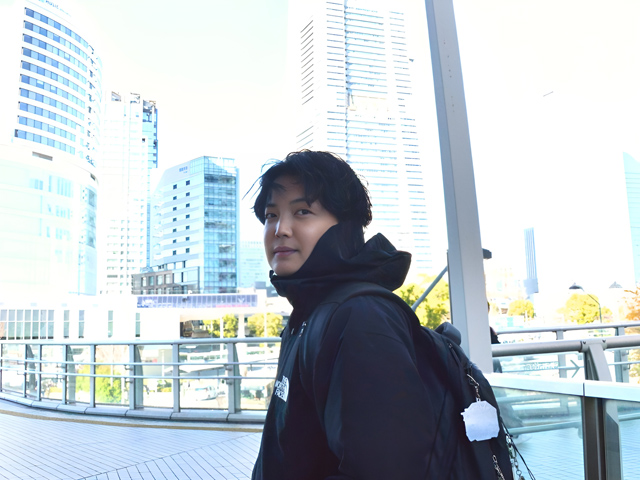
【2026年最新】心霊TikToker山ちゃんが警告! 年始・初詣シーズンに避けるべき日本の「運気が下がる最恐スポット」
2026.01.11 エンタメ -

「難病の母の入院費が…」涙ながらに100万円を要求してきた“ホスト彼氏持ち女”の恐怖手口
2026.01.11
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

開幕前に解任確定!? 生みの親・原辰徳氏にまで見限られた巨人・阿部監督の“四面楚歌”
2026.01.10 スポーツ -
秋元康の大ブレイクのきっかけとなった“冬の昭和歌謡” 菊池桃子『雪にかいたLOVE LETTER』
2026.01.11 エンタメ -

山口智子、ガムテープと手錠を持った暴漢2人が自宅に突撃〜女性芸能人暴行事件史④
2021.12.30 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -

「自信があるから産んだんです」略奪愛も辞さなかった恋多き女優・萬田久子の覚悟と代償
2024.11.10 芸能 -
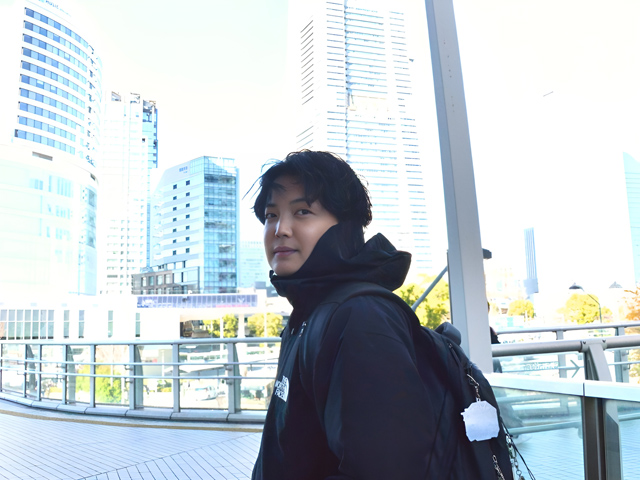
【2026年最新】心霊TikToker山ちゃんが警告! 年始・初詣シーズンに避けるべき日本の「運気が下がる最恐スポット」
2026.01.11 エンタメ -

「難病の母の入院費が…」涙ながらに100万円を要求してきた“ホスト彼氏持ち女”の恐怖手口
2026.01.11

