党内を敵に回した反逆児・石破茂首相が突き進む「自公立大連立」の“青写真”
浮かんでは消え、消えては浮かぶ自民党と立憲民主党などの大連立構想。石破茂首相は実現に向け、腹を固めたようだ。
両党の接着剤となるのは公明党。自公立政権は「中道政権」にほかならず、自民内では旧安倍派、立憲内では枝野幸男元代表ら左派勢力が反発するのは必至。だが、石破首相は反逆児よろしく強行突破する構えだ!
【関連】党内は“石破おろし”に手ぐすね! トランプ会談成功の石破政権が企む苦し紛れの「4月解散」延命策 ほか
首相は新たな中選挙区制度を提唱
トランプ米大統領との初の首脳会談の成果については賛否が渦巻いているが、当の石破首相は昨年10月の第1次内閣発足後、衆院選で惨敗したにもかかわらず居座りを決め込み、自民党内は静寂を保っている状況だ。
それもそうだろう。内閣支持率は低迷したままだが、敵対勢力である旧安倍派は衆院選で相次いで落選。安倍晋三元首相を慕う高市早苗前経済安全保障担当相は「ポスト石破」を狙うが、勢いはない。
少数与党政権であっても、「石破おろし」が起きていないことは不幸中の幸いと言えよう。
とはいえ、政権運営は決して楽ではない。
全国紙政治部デスクはこう語る。
「自民は『年収103万円の壁』の見直しを巡り、国民民主党と神経戦を繰り広げ、日本維新の会とは高校授業料無償化の対応で苦戦しています。“個別の政策ごとにチマチマと政策協議なんて付き合っていられない”が自民執行部の本音です」
自民と立憲との大連立構想が消えないどころか、日に日に現実味を増しているのは、このあたりに理由がありそうだ。
大連立の「大義」となり得るのは、石破首相が持論とする「中選挙区連記制」の実現にほかならない。
これまで雑誌などで「全国に定数3の中選挙区を150作って、有権者は各選挙区で3人まで候補者を選ぶ」制度を提唱しているのだ。
公明党も立憲にすり寄り
そして、自民と立憲をくっつけようとしているのが公明だ。
昨年10月の衆院選で、小選挙区の立候補者11人の全員当選を目標に掲げたが、維新と対決した大阪府の4選挙区すべてで落選。北海道、愛知、石井啓一前代表が出馬した埼玉の選挙区でも落選し、4勝7敗の憂き目に遭った。
中小政党に共通する悩みのタネの小選挙区制は、2大政党政治を前提にしているため、公明は大政党の陰に埋もれ、当選させるのは至難の業。中選挙区制のほうが“生き残り”の活路を見いだしやすいのだ。
立憲は選挙制度改革に対して意見が割れているが、小選挙区制の下での政権交代の可能性に限界を感じているのは事実。ならば中選挙区制をベースにした選挙制度に変え、多党制を実現させ連立政権を模索したほうが政権交代の可能性はぐっと高まる。
立憲内では徐々にではあるが、そんな見方が強まりつつある。
要は「細川護熙政権モデル」である。
全国紙政治部記者は「公明が選択的夫婦別姓の導入にこだわり、立憲に接近しているのは、もちろんそれを導入したいという思いはあるのですが、中選挙区連記制を実現するための立憲取り込み作戦の一環という側面もあるのです」と語る。
【永田町裏情報2】へ続く
「週刊実話」2月27日号より
合わせて読みたい
-

今田美桜の事務所に3億円訴訟!“芸能界のドン”激怒で活動危機か
2025.12.08 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

【現役ドラフト2025】2巡目ゼロの大異常と“実質トレード化”が深刻化…「もはや制度崩壊」の声も
2025.12.10 スポーツ -

ハラスメント調査対象の大物タレントA「たけし呼び捨て」「東の島田紳助」過去行状
2025.08.11 芸能 -
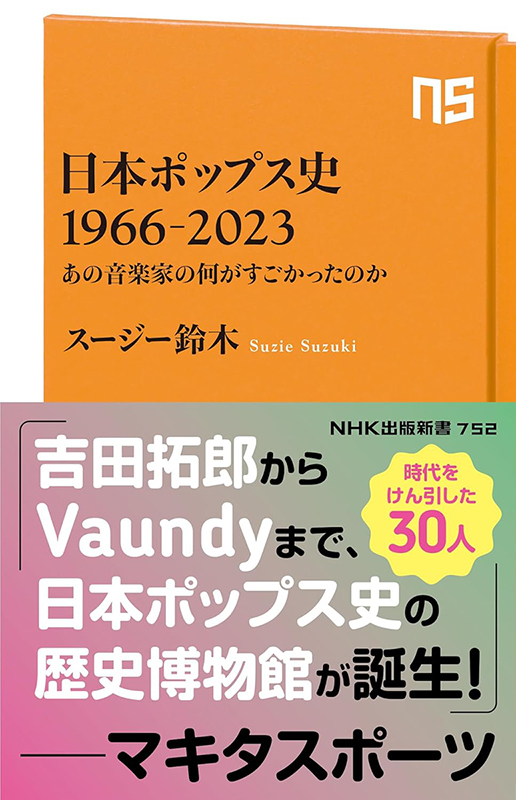
「最大の存在は吉田拓郎」音楽評論家が“日本ポップス史”を徹底解説!
2025.12.10 エンタメ -

美術留学から帰国した娘が全身タトゥー&ピアスだらけ!「身体に施した芸術」を巡る壮絶父娘ケンカ
2025.12.10 -

『ゴッドタン』悪行暴露された元アイドルの女芸人は誰?ペットヒントに特定班動く
2022.12.17 芸能 -

岡田奈々“性的暴行被害”もささやかれた「自宅監禁」恐怖の5時間〜女性芸能人暴行事件史①
2021.12.30 芸能 -

「歌詞は美しく、とても物悲しい」日本レコード大賞を受賞した布施明の『シクラメンのかほり』
2025.12.09 エンタメ
合わせて読みたい
-

今田美桜の事務所に3億円訴訟!“芸能界のドン”激怒で活動危機か
2025.12.08 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

【現役ドラフト2025】2巡目ゼロの大異常と“実質トレード化”が深刻化…「もはや制度崩壊」の声も
2025.12.10 スポーツ -

ハラスメント調査対象の大物タレントA「たけし呼び捨て」「東の島田紳助」過去行状
2025.08.11 芸能 -
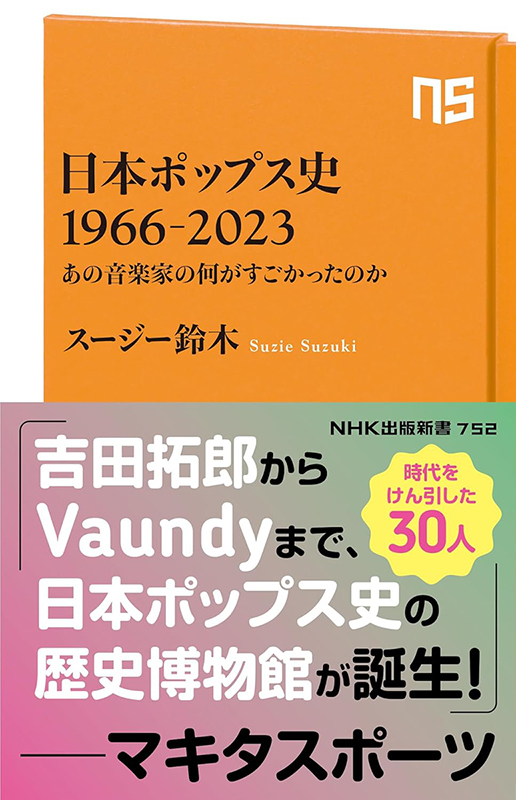
「最大の存在は吉田拓郎」音楽評論家が“日本ポップス史”を徹底解説!
2025.12.10 エンタメ -

美術留学から帰国した娘が全身タトゥー&ピアスだらけ!「身体に施した芸術」を巡る壮絶父娘ケンカ
2025.12.10 -

『ゴッドタン』悪行暴露された元アイドルの女芸人は誰?ペットヒントに特定班動く
2022.12.17 芸能 -

岡田奈々“性的暴行被害”もささやかれた「自宅監禁」恐怖の5時間〜女性芸能人暴行事件史①
2021.12.30 芸能 -

「歌詞は美しく、とても物悲しい」日本レコード大賞を受賞した布施明の『シクラメンのかほり』
2025.12.09 エンタメ

