「王貞治からホームラン王を奪う」阪神入団拒否から3代目ミスタータイガースに上り詰めた田淵幸一の矜持
「日本に帰ったら、また王さんにやられるんだろうな」
初のホームラン王になったこの年のオフ、筆者に「田淵をテーマにした連載を書け」というミッションが会社から下った。
ちょうど結婚したばかりの田淵夫妻が本塁打王の褒美としてオーストラリア旅行に行くことになり、その同行レポートを書くというものだった。
旅行には田淵の飲み友達でこのシーズンに活躍した遠井吾郎、安仁屋宗八夫妻も同行した。当時の海外旅行はまだまだ高価で出発前はかなり緊張したが、その心配は無用だった。
筆者は結婚前から田淵夫妻の相談に乗っており、結婚のスクープもさせてもらっていた。そのため夫人とも面識があり、すぐリラックスした雰囲気に溶け込むことができたのだ。
ケアンズのビーチで田淵がサングラスをかけて大笑いする姿をカメラに収め、夜はワインを片手に「日本に帰ったら、(本塁打王争いで)また王さんにやられるんだろうな」といった本音をじっくりと聞いた。
ある夜には夫人たちが寝た後に男たちだけで部屋を抜け出し遊郭街に繰り出したこともあった。案内役を買って出た筆者の英語下手のせいで目的の店には行けなかったが、それも今となってはいい思い出だ。
ホテルの一室で原稿用紙を広げ、眠気と格闘しながら執筆した連載は大好評。帰りの飛行機の中で書いた最終回ではこっそり田淵本人に文章を書いてもらい、誰にも言わず送稿した。
デスクから戻ってきた感想は「特に最終回が最高だな」。やはり、“本物の言葉”はそれだけで魅力があるのだと痛感した。
この時期は田淵にとっても阪神ファンにとっても幸せな時期だったはずだ。優勝こそ逃していたが、江夏と田淵の黄金バッテリーを中心に宿敵・巨人を追い詰め、数々の名勝負を見せてくれた。
だが、誰よりも華やかに見えた田淵の野球人生は次第に難しい局面を迎えていくことになる。それは「ミスタータイガース」という称号が持つ負の側面によるものだった。
(後編に続く)
「週刊実話」10月2・9日号より
吉見健明
1946年生まれ。スポーツニッポン新聞社大阪本社報道部(プロ野球担当&副部長)を経てフリーに。法政一高で田淵幸一と正捕手を争い、法大野球部では田淵、山本浩二らと苦楽を共にした。スポニチ時代は“南海・野村監督解任”などスクープを連発した名物記者。『参謀』(森繁和著、講談社)プロデュース。著書多数。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

土屋太鳳のボディータッチにジャニオタ悲鳴!「触らないで!」イベントで絶叫
2022.01.26 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -
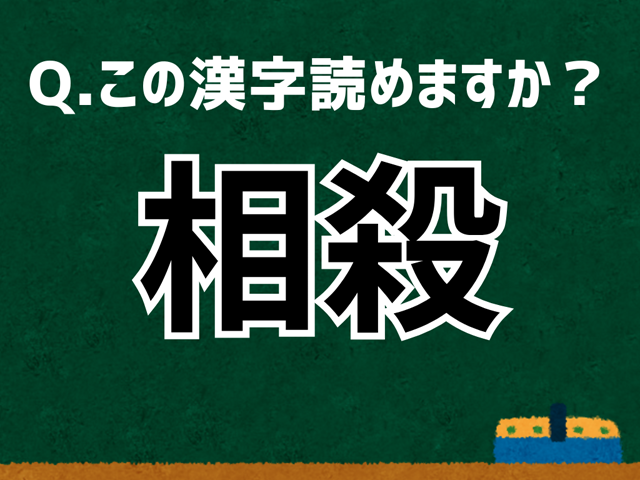
「相殺」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.11 エンタメ -

久米宏司会の音楽番組『ザ・ベストテン』伝説の初回1位! 歌謡界“黄金時代”の一翼を担ったピンク・レディー『UFO』
2026.02.11 エンタメ -

平野歩夢、複数骨折からの“強行出陣”。逆境を越えて挑む「不屈の系譜」
2026.02.11 スポーツ
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

土屋太鳳のボディータッチにジャニオタ悲鳴!「触らないで!」イベントで絶叫
2022.01.26 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -
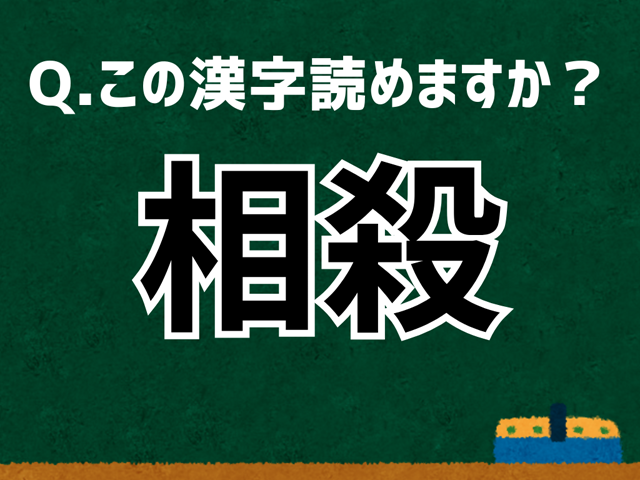
「相殺」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.11 エンタメ -

久米宏司会の音楽番組『ザ・ベストテン』伝説の初回1位! 歌謡界“黄金時代”の一翼を担ったピンク・レディー『UFO』
2026.02.11 エンタメ -

平野歩夢、複数骨折からの“強行出陣”。逆境を越えて挑む「不屈の系譜」
2026.02.11 スポーツ

