「官邸主導になってから日本経済は成長していない」森永卓郎さんが考えるキャリア官僚の人気が下がった理由

今年4月から本格導入の運びとなったが、この流れが地方に波及し昨年6月には千葉県が地方公務員にこの制度を導入。年末には東京都が2025年度からの導入を発表したことで拍車がかかり、次々と手を上げる地方自治体が増え続けている。
だが、この制度の導入に異を唱えていたのが、今年1月に亡くなった経済アナリストの森永卓郎氏だ。
週刊実話2023年5月11・18日号掲載「国家公務員の週休3日制」より ※肩書などは当時のもの
週休3日制を導入する民間企業はわずか2%
4月14日付の日本経済新聞が「国家公務員、週休3日制拡大」と伝えた。
新卒者の「霞が関離れ」を食い止めるために、多様な働き方を認めるのだという。今夏の人事院勧告に盛り込む方向で、検討するとのことだ。
確かに、霞が関の官僚となるための国家公務員総合職への応募者が、減少傾向にあることは事実だ。ただ、それでも応募倍率は10倍程度の狭き門になっている。
また、総合職で採用されるのは1200人程度で、国家公務員に採用される人数の1割強にすぎない。日本の未来を左右するエリート中のエリートが、国家公務員総合職、キャリア官僚なのだ。
だが、その人気が下がっていることを口実に、公務員全体に週休3日制を導入するのはいかがなものか。週休3日制を導入している民間企業は、わずか2%しかないのが現状なのだ。
じつは同じようなことが、国家公務員の定年延長でも起きている。
今年から国家公務員の定年を65歳へと、2年に1歳ずつ延長する制度改正が始まった。民間企業で65歳以上の定年を定めている企業は、25%しかない。
さらに国家公務員の賃金は、民間企業より3割も高くなっている。定年延長にしても、週休3日制にしても、高賃金にしても、人事院のやっていることは、お手盛りとも言えるものだ。
私は、キャリア官僚の人気が下がっている理由は、仕事がつまらなくなっていることと、残業代が支払われないことだと思う。
昔から残業代は支払われなかったが、その分、退官後の天下り先での処遇で、十分に元が取れていた。
いまは天下りのあっせんが禁じられ、退職後の保証がなくなってしまった。天下りを復活させることはできないから、官僚には働いたら働いた分だけ、賃金を支払えばよい。
【関連】国民負担率上昇は高齢者の責任なのか? 選挙へ行かない若年層は「実質的に増税を容認している」 ほか
- 1
- 2
合わせて読みたい
-

スタプラ新星「RE-GE」始動にファン複雑―― AMEFURASSHIら“解散発表”から2カ月、素直に祝えない理由
2026.02.19 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

布袋寅泰の妻・山下久美子に「好きな人がいるの」と相談した今井美樹の外道ぶり【美女たちの不倫履歴書10】
2023.05.06 芸能 -

RIKACOから渡部篤郎を“略奪”同棲したものの銀座の女に乗り換えられた中谷美紀【美女たちの不倫履歴書9】
2023.05.06 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

【激震】 Snow Manが『ザ!鉄腕!DASH!!』の後継に? 日テレが狙う「世界配信バラエティー」への世代交代
2026.02.21 芸能 -
闇バイトはなぜ拡大したのか? 裏社会の専門家が明かす“トクリュウ”の実態
2026.02.22 エンタメ -
【豊臣兄弟!トリビア】戦国きっての“イケメン”だった軍師・竹中半兵衛の美貌とインテリジェンス
2026.02.22 エンタメ -
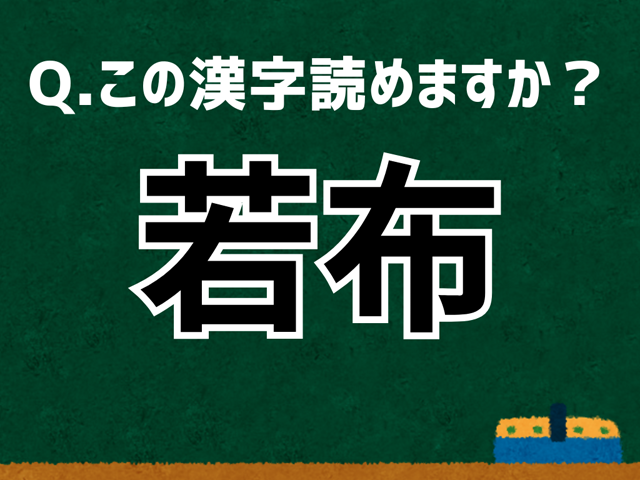
「若布」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.21 エンタメ -
日本でラップブーム到来前の“韻革命”! 庄野真代『飛んでイスタンブール』の衝撃
2026.02.21 エンタメ
合わせて読みたい
-

スタプラ新星「RE-GE」始動にファン複雑―― AMEFURASSHIら“解散発表”から2カ月、素直に祝えない理由
2026.02.19 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

布袋寅泰の妻・山下久美子に「好きな人がいるの」と相談した今井美樹の外道ぶり【美女たちの不倫履歴書10】
2023.05.06 芸能 -

RIKACOから渡部篤郎を“略奪”同棲したものの銀座の女に乗り換えられた中谷美紀【美女たちの不倫履歴書9】
2023.05.06 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

【激震】 Snow Manが『ザ!鉄腕!DASH!!』の後継に? 日テレが狙う「世界配信バラエティー」への世代交代
2026.02.21 芸能 -
闇バイトはなぜ拡大したのか? 裏社会の専門家が明かす“トクリュウ”の実態
2026.02.22 エンタメ -
【豊臣兄弟!トリビア】戦国きっての“イケメン”だった軍師・竹中半兵衛の美貌とインテリジェンス
2026.02.22 エンタメ -
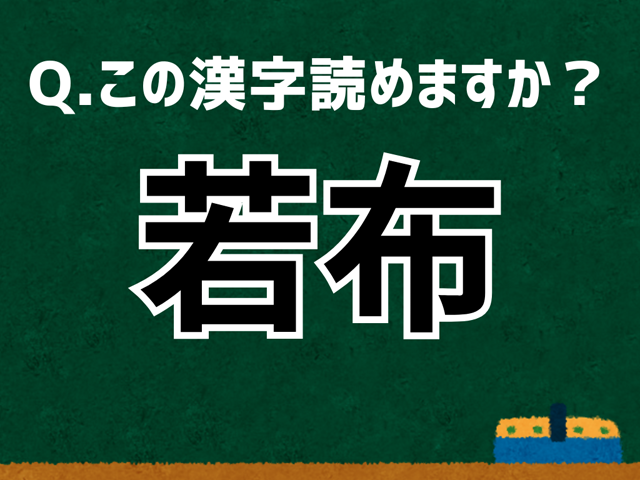
「若布」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.21 エンタメ -
日本でラップブーム到来前の“韻革命”! 庄野真代『飛んでイスタンブール』の衝撃
2026.02.21 エンタメ

