【戦後80年】肉の配給は月イチ1人37グラム 当時の主婦が知恵を絞った肉レシピ
2025.08.14

戦争中でも戦時下でも食料は貴重な存在だったため、食料を節約するため、さまざまな工夫がなされていたようだ。
肉の配給は1人あたり月に37グラム
1940年(昭和15年)4月7日に農林省(現・農林水産省)は、東京をはじめ全国の主要都市で「肉なしデー」を実施することを決めた。
すでに肉はぜいたく品であるとの考えが広まっていたため、真っ先にやり玉に挙げられたのだ。
これにより毎月2回、のちには週1回、肉の販売や食堂での肉料理の提供が禁止された。
ただし、名古屋では同年5月8日から、東京では翌年の5月8日からと、多少は施行日の前後があったものの、その熱は高かったという。
「肉なしデー」の日、肉屋は一斉休業、飲食店では肉の入った料理を一切出さないという号令の下で行われ、カレーライスの中に小さな肉切れが入っていたとして、非難された飲食店もあったという。
しかし、日中戦争の長期化で食糧が不足し、すでに肉屋の店頭には牛肉が従来の3分の1、豚肉にいたってはほとんど売っていなかった。
そして“闇肉”は非常に高値で、おいそれと庶民は手を出せなかったため、実際のところ「肉なしデー」はあってもなくても同じだったという。
配給制に変わっても、肉の配給は月に1度で、量も1人37グラムまでという少なさである。
- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

キムタク長女・Cocomiに男子バレーファンが嫉妬!? 一人歩きする“おかしなウワサ”とは
2024.06.14 芸能 -

綾瀬はるか、30代ラストイヤーに結婚断念!? 仕事をセーブするも周囲にこぼした諦めムード
2024.06.01 芸能 -
大沢あかね&劇団ひとりに“離婚説”が再浮上!「プライベートで何かトラブルが…」疑念広がる
2025.03.21 芸能 -
綾瀬はるか&ジェシー紅白共演で浮上する「元日入籍」と極秘妊娠説
2025.12.18 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

「結婚しないで歌手でいれば…」長渕剛に三行半を突き付けた石野真子の離婚の真相【週刊実話お宝記事発掘】
2024.10.31 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -
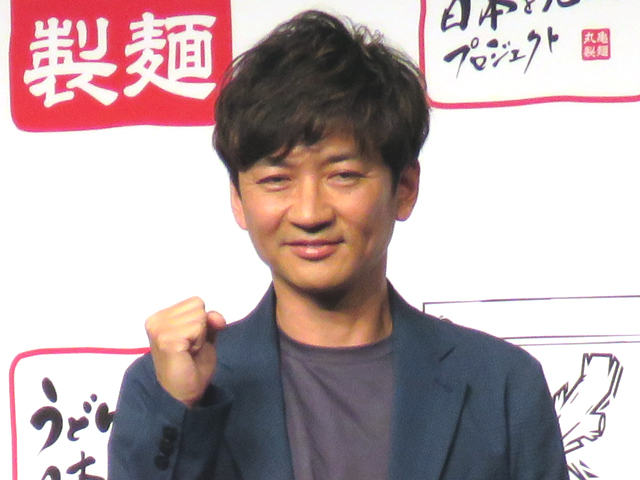
国分太一「答え合わせできないまま降板」会見で語った“コンプラ違反”の真相とは?
2025.11.27 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

キムタク長女・Cocomiに男子バレーファンが嫉妬!? 一人歩きする“おかしなウワサ”とは
2024.06.14 芸能 -

綾瀬はるか、30代ラストイヤーに結婚断念!? 仕事をセーブするも周囲にこぼした諦めムード
2024.06.01 芸能 -
大沢あかね&劇団ひとりに“離婚説”が再浮上!「プライベートで何かトラブルが…」疑念広がる
2025.03.21 芸能 -
綾瀬はるか&ジェシー紅白共演で浮上する「元日入籍」と極秘妊娠説
2025.12.18 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

「結婚しないで歌手でいれば…」長渕剛に三行半を突き付けた石野真子の離婚の真相【週刊実話お宝記事発掘】
2024.10.31 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -
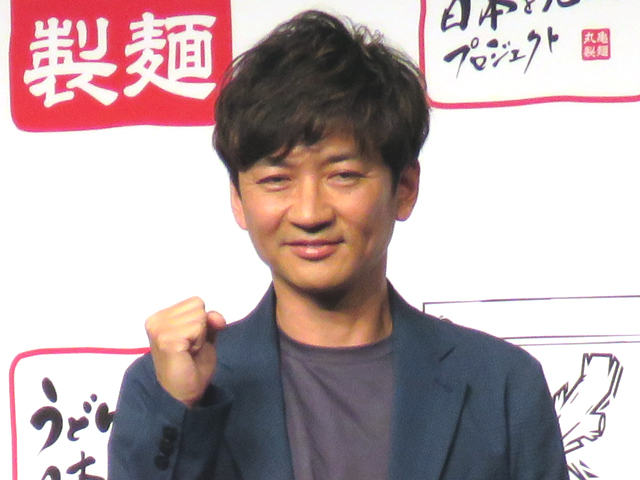
国分太一「答え合わせできないまま降板」会見で語った“コンプラ違反”の真相とは?
2025.11.27 芸能

