カレーは「辛味入り汁かけ飯」に…太平洋戦争時「金属製曲がり尺八」と呼ばれた楽器は?
2025.07.19

英語は軽佻浮薄で“敵性言語”に
大正ロマンの時代から昭和モダンの時代となり、日本は貪欲に西洋の文化を取り入れ、人々は我先にと初めて見る舶来品に飛びついた。
音楽ではジャズやタンゴが大流行し、洋画が人気を集め、東京の銀座には洋装のモダンガール、モダンボーイが登場。洋行帰りの実業家たちは、本場仕込みの触れ込みで洋食レストランをあちこちに開業し、ライスカレーやオムライス、お子様ランチが外食の定番になった。
昭和初期の日本は北から南まで、洋風かぶれの時代だったのである。
ところが、日本が中国と一触即発の状態に陥ると、中国側を支援するアメリカやイギリスとの溝が深まり、次第に日本は米英を敵性国家と見なすようになる。
すると、英語は軽佻浮薄(けいちょうふはく)なうえに“敵性言語”であるとして、排斥の動きが起こり始めた。
例えば、庶民に娯楽を提供していた映画界では、内務省の指示によりカタカナ名の芸能人がこぞって改名させられ、ディック・ミネは「三根耕一」に、ミス・コロンビアは「松原操」になった。
太平洋戦争で米英が完全な敵国になると、その動きはより露骨なものとなる。
ジャズやクラシックなどは敵性音楽として禁止され、国民学校の卒業式では『蛍の光』がスコットランド民謡を原曲にしているとして、『海行かば』などの愛国歌に変更された。
- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉
2022.08.17 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
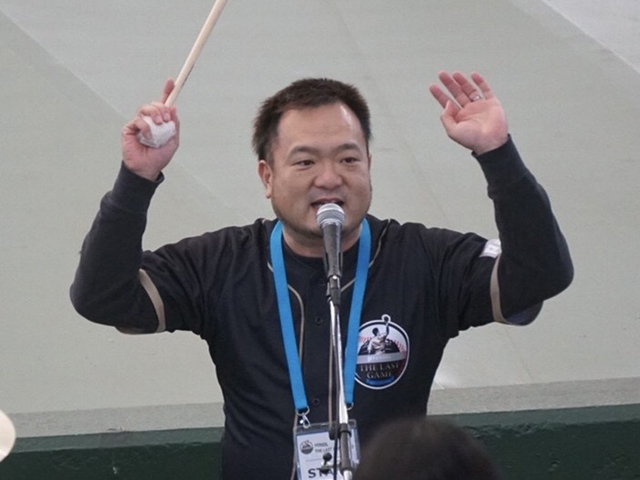
「応援は人生を代償にしてこそ美しい」プロ野球応援の革命児が栄光と挫折の末にたどり着いた真髄を激白!
2025.03.17 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

人型、巨獣、異形…江戸時代を跋扈した多様なUMAの世界! 木こりの仕事を手伝うUMAは何者か
2026.01.10 エンタメ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -
%20(1).jpg)
「2026年完成」の“嘘”に隠されたサグラダ・ファミリア「住民3000人立ち退き問題」と「暴走する観光マネー」
2026.01.09 -
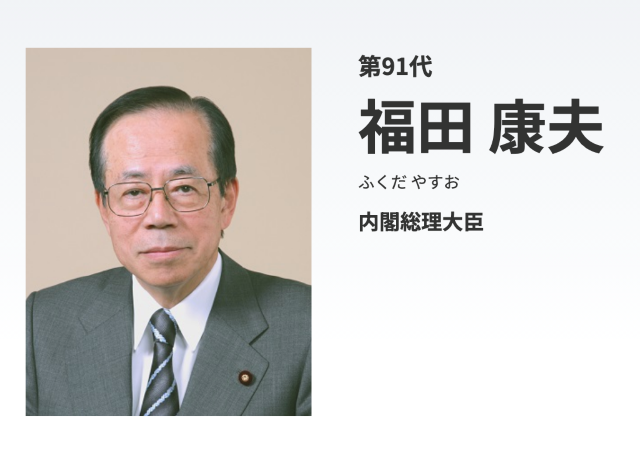
幻に終わった大連立構想、政権発足から約1年で退陣…福田康夫に欠けていた“総理の器”
2026.01.10 -

たぬかな今度こそ完全終了?“ホロコースト揶揄”で完全に一線を超えるも反省の色ナシ「ガス室送るぞ」
2024.04.27 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉
2022.08.17 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
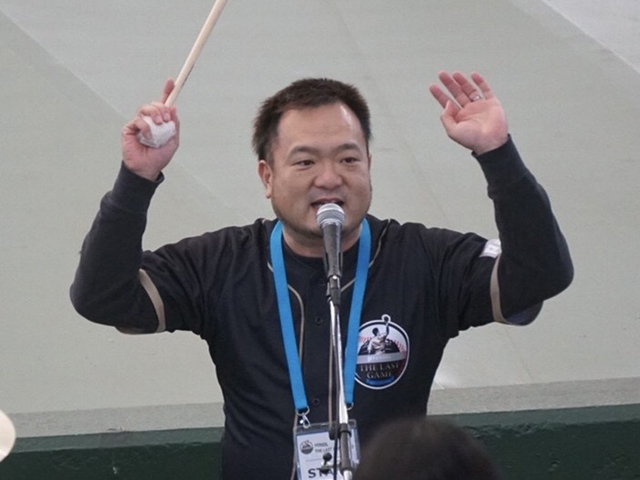
「応援は人生を代償にしてこそ美しい」プロ野球応援の革命児が栄光と挫折の末にたどり着いた真髄を激白!
2025.03.17 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

人型、巨獣、異形…江戸時代を跋扈した多様なUMAの世界! 木こりの仕事を手伝うUMAは何者か
2026.01.10 エンタメ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -
%20(1).jpg)
「2026年完成」の“嘘”に隠されたサグラダ・ファミリア「住民3000人立ち退き問題」と「暴走する観光マネー」
2026.01.09 -
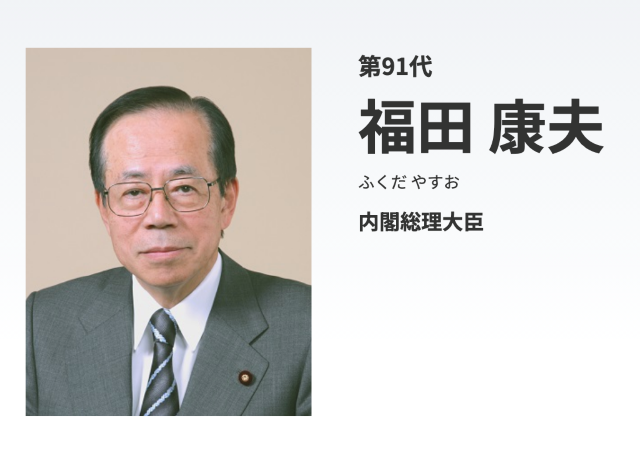
幻に終わった大連立構想、政権発足から約1年で退陣…福田康夫に欠けていた“総理の器”
2026.01.10 -

たぬかな今度こそ完全終了?“ホロコースト揶揄”で完全に一線を超えるも反省の色ナシ「ガス室送るぞ」
2024.04.27 芸能

