「若者が死ぬことで将来の高齢者が減り、年金が救われる」森永卓郎さんが考えていた“恐ろしい未来予想図”
2025.05.02
「公表されてきた『年齢別労働力供給の想定』が記載されていない」

働き続ける期間を延ばせば、年金保険料を負担する人口が増える。一方で年金受給者は減るから、年金財政の改善効果は大きい。
実際、2019年に行われた前回の財政検証で「経済成長と労働参加が進むケース」の推計を見ると、2040年の労働力率は、男性の65~69歳が71.6%、70~74歳が49.1%、女性の65~69歳は54.1%、70~74歳が32.6%となっていた。
つまり、男性の4人に3人が70歳まで働き、約半数が75歳まで働く。女性の過半数が70歳まで働き、3人に1人が75歳まで働く。そうした条件が満たされて初めて、日本の公的年金制度を維持することができるというのだ。
70歳まで働き続けるのは、厳しいけれど不可能ではない。問題は男性の半数、女性の3分の1が75歳まで働くという前提だ。
例えば、厚労省が公表した2020年の「健康寿命」で見ると、男性は72.57歳、女性は75.45歳なので、75歳まで働き続けることはかなり難しいのだ。
それでは今回の財政検証で、労働力率の想定はどうなったのか。不思議なことに今回の財政検証の資料には、これまでずっと公表されてきた「年齢別労働力供給の想定」が記載されていない。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -
戦慄! 高市早苗「316議席獲得」で起こる“巨大与党誕生”のヤバすぎる代償
2026.02.09 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
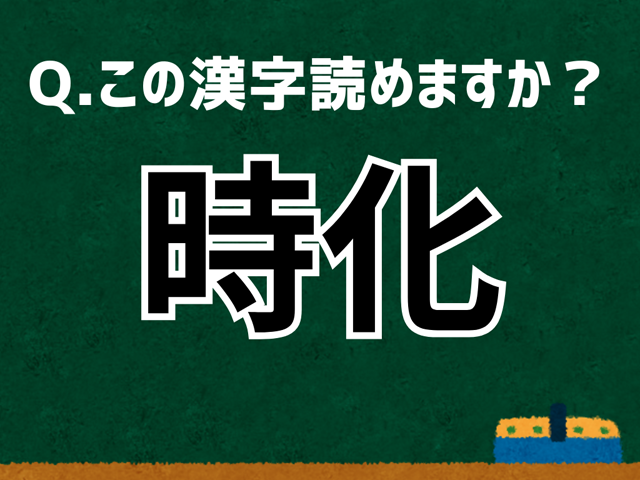
「時化」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.09 エンタメ -

WBC日本代表2026 メジャー組が最多9人 NPBの未来はどう変わる
2026.02.09 スポーツ -

石田ゆり子に大人の写真集待望論も! 超絶トレーニング動画に「体幹がエグい」とファン騒然
2026.02.07 芸能 -
戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”
2025.11.16 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -
.jpg)
球界最遅契約更改...阪神サトテル"国内ラストイヤー"既定路線
2026.02.09 スポーツ -

高木美帆が魅せる16年目の集大成。1000メートルで“究極の機能美”が完成する
2026.02.09 スポーツ
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -
戦慄! 高市早苗「316議席獲得」で起こる“巨大与党誕生”のヤバすぎる代償
2026.02.09 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
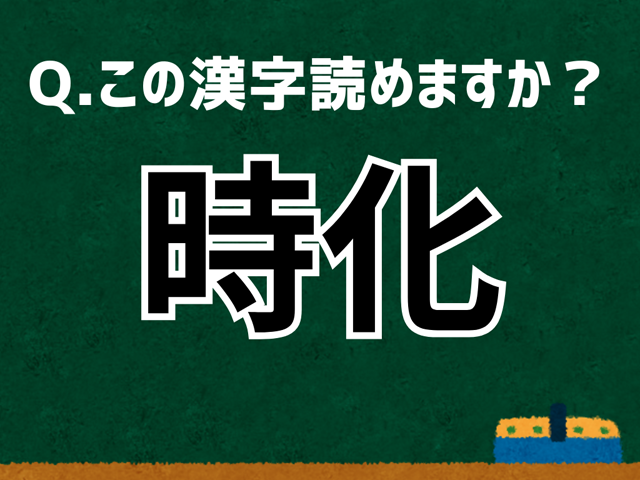
「時化」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.09 エンタメ -

WBC日本代表2026 メジャー組が最多9人 NPBの未来はどう変わる
2026.02.09 スポーツ -

石田ゆり子に大人の写真集待望論も! 超絶トレーニング動画に「体幹がエグい」とファン騒然
2026.02.07 芸能 -
戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”
2025.11.16 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -
.jpg)
球界最遅契約更改...阪神サトテル"国内ラストイヤー"既定路線
2026.02.09 スポーツ -

高木美帆が魅せる16年目の集大成。1000メートルで“究極の機能美”が完成する
2026.02.09 スポーツ

