“竹下流”とは剛速球でなくチェンジ・オブ・ペース 森喜朗に「天才」と言わしめた竹下登のリーダーシップ
本人は「組織のムードメーカー」と論評
竹下はさらりと、こう答えてくれたものであった。
「僕は、何事も説得しつつ推進し、推進しながら説得するということに徹したわな。これ以外の手は、ほぼない。みんなの意見を聞き、自分はかく思うとは言わないということだ。
このほうが、万事うまくいく。それと、人が持ってくる話でも、大方は『そうだわな』『話は分かった』くらいしか答えない場合が多い。確約してしまうと、あとで身動きが取れなくなるからだ。
僕は相手に言質を与えてしまうことには、慎重なタイプだ。また、自分から『ああしろ』『こうしろ』と指示、命令も、まずしないね。自分から積極的に方向性を示すことはしない。まぁ、人はいろいろと言うが、僕は組織のムードメーカーといったところじゃないかな」
ましてや人を怒ることなどは、とんでもないと言いたげだった。
竹下の出身校である早稲田大学の創立者、大隈重信(元首相)は気が短く、誰彼構わず怒鳴りつけたことで知られていた。
しかし、やがて首相になる頃には、この欠点がすっかり影を潜めたといわれている。
側近格だった実業家の五代友厚から、「短気は政治家として大きなマイナス」として、次のような進言を受けたからであった。
「怒気怒声を発するは、一の益あるかを聞かず。怒気怒声を発すれば、その徳望を失する原因なり」
その竹下は、しかし一方で長期政権の可能性を示唆されながら、わずか2年間で政権の座から降りることになった。
「政治とカネ」をめぐる問題、すなわちリクルート事件に連座し、平成元(1989)年6月に、退陣を余儀なくされたのである。
その独特なリーダーシップは、画竜点睛を欠く形で幕が引かれた。
竹下の退陣後、自民党の実力者2人は、こう「竹下観」を述べていた。
「政界という組織の力学を、これほど分かっている人はいなかった。その点では天才と言ってよかった」(森喜朗元首相)
「人をうまく使い、統率していく名人だった。その限りにおいては、この人の右に出る人はいなかった。さしもの田中角栄元首相も、この点では及ばなかった」(後藤田正晴元副総理)
(文中敬称略/次回は宇野宗佑)
「週刊実話」5月8・15日号より
【関連記事】竹下登は「気配りで天下を取った唯一の男」田中角栄と双璧をなす“座持ちのうまさ”を元関係者たちが証言
小林吉弥(こばやし・きちや)
政治評論家。早稲田大学卒。半世紀を超える永田町取材歴を通じて、抜群の確度を誇る政局・選挙分析に定評がある。最近刊に『田中角栄名言集』(幻冬舎)、『戦後総理36人の採点表』(ビジネス社)などがある。
- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

阪神・佐藤輝明“電撃引退”へ 交渉決裂間近で目指す“浪人メジャー移籍”というウルトラC
2026.01.22 スポーツ -

和久田麻由子アナNHK退局で争奪戦!日テレ・テレ朝が「1億円」提示で白羽の矢
2026.01.18 芸能 -
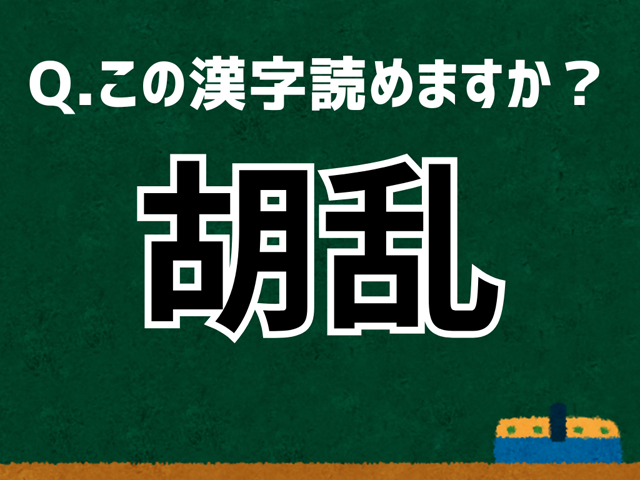
「胡乱」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.01.29 エンタメ -
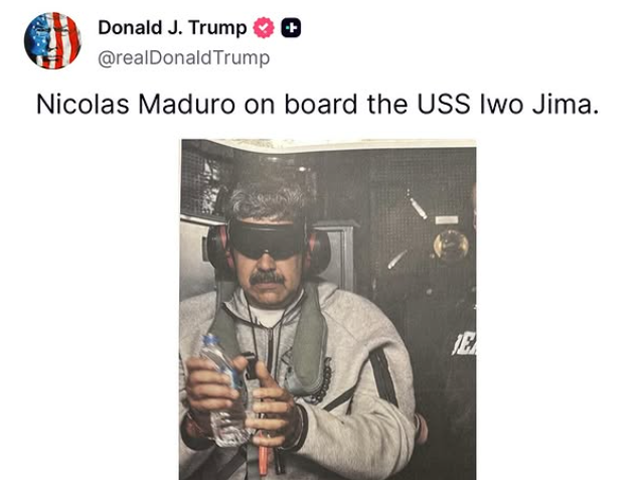
世界覇権の野望 トランプ大統領が石油・レアアース強奪
2026.01.29 -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ
2025.09.03 スポーツ -

カープ羽月隆太郎、ゾンビたばこで逮捕の衝撃と「バティスタみたいになりたい」の悲しき伏線
2026.01.29 スポーツ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
綾瀬はるか“長澤まさみ元日婚”に対抗? ジェシーと「妊娠・結婚」同時発表説が濃厚に
2026.01.29 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

阪神・佐藤輝明“電撃引退”へ 交渉決裂間近で目指す“浪人メジャー移籍”というウルトラC
2026.01.22 スポーツ -

和久田麻由子アナNHK退局で争奪戦!日テレ・テレ朝が「1億円」提示で白羽の矢
2026.01.18 芸能 -
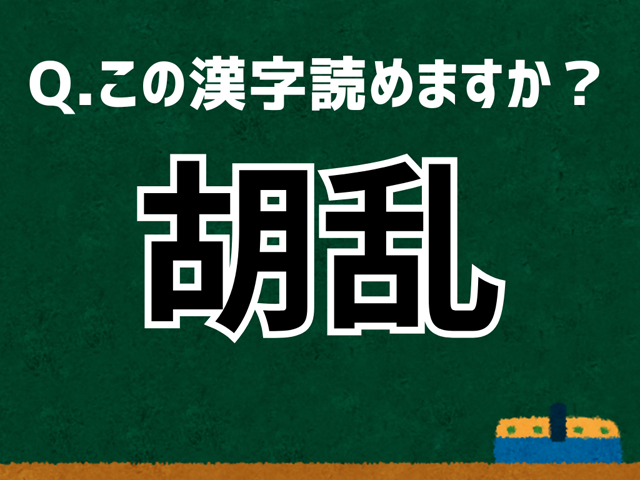
「胡乱」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.01.29 エンタメ -
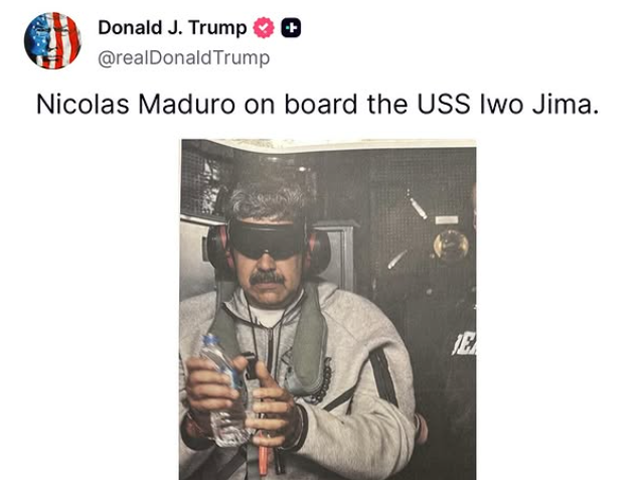
世界覇権の野望 トランプ大統領が石油・レアアース強奪
2026.01.29 -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ
2025.09.03 スポーツ -

カープ羽月隆太郎、ゾンビたばこで逮捕の衝撃と「バティスタみたいになりたい」の悲しき伏線
2026.01.29 スポーツ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
綾瀬はるか“長澤まさみ元日婚”に対抗? ジェシーと「妊娠・結婚」同時発表説が濃厚に
2026.01.29 芸能

