
DCコミック実写で一番燃える!『ワンダーウーマン 1984』に心湧く〜LiLiCo☆肉食シネマ~
『ワンダーウーマン 1984』 監督・脚本/パティ・ジェンキンス 出演/ガル・ガドット、クリステン・ウィグ、クリス・パイン、ロビン・ライト、ペドロ・パスカル、コニー・ニールセン 配給/ワーナー・ブラザース映画
予定していた大作映画のほとんどが、公開延期になった2020年。唯一、10月に公開された『テネット』は記憶に新しいけど、あとはミニシアター系の作品でしたね。誰もが〝大作!〟と思う作品に飢えてると思い、今回『ワンダーウーマン 1984』を選びました。
【関連】『レディ・トゥ・レディ』/12月11日(金)より全国ロードショー~LiLiCo☆肉食シネマ ほか
まず、これは前作の続編ですが、初めて見る人でも全く問題ありません! もちろん、細かいことを事前に知っておくと、より楽しむことはできますが、「前作を見てないからなぁ~」と言ってスルーするには、あまりにもったいない。最高のアクションはもちろんのこと、人間の内面の強さなども、描かれています。
本編では、前作で亡くなってしまったはずのダイアナ(ワンダーウーマン)の恋人・スティーブが突然、現れます。これはなぜ? …と、ラブストーリー要素もありますが、私がワクワクしたのは3つ。
1つは、普段は身分を隠して考古学者として働くダイアナの同僚・バーバラが、めちゃくちゃ楽しい。ワンダーウーマンファンはもちろん知っていますが、知らない人が見ても、彼女のテンションに心が湧くはず。
DCコミック実写作品で一番燃えました!
2つ目は、すごいパワーを手に入れて、何でも叶ってしまうマックスに注目です。とにかく、こんなに分かりやすい悪役は、他にはいません! 見ていて気持ちがイイくらい!そして最後は、1984年という時代設定。あの頃が青春だった世代の人たちにとっては懐かしい光景が広がる、その映像美がすごいんです! 冒頭から引き込まれてしまいます。
最強のヒーローのパワーが弱まってしまう、というDCコミックならではの心の中の葛藤も描かれているからこそ、大人にも人気のシリーズ。前作から引き続き、監督を努めるのはパティ・ジェンキンス! ダイナミックに、そして、時にユーモラスにワンダーウーマンとその世界を描いています。今まで見たDC実写作品で一番燃えました。
さらに、コアなファンにとっては、〝とうとう登場するのか!〟と唸るキンキラキンのゴールドアーマー。私も思わず心の中で〝YES!〟と叫んでしまいましたが、実は撮影は大変だったそう。というのも、ゴールドアーマーは鏡みたいにいろんなものを〝綺麗〟に写してしまうため、まわりのスタッフが丸見えになるエピソードも…。でも、そんな裏話にも、思わずほっこりさせられました。
合わせて読みたい
-

40歳・小倉優子“年内に3度目の結婚”の可能性!?「どんどんキレイになってる」若返りの裏側
2024.07.22 芸能 -

『Snow Man』メンバーで一番“演技下手”なのは…業界内で「期待ハズレ」とささやかれる演技力
2024.07.24 芸能 -
AKB48の新曲売上が15年ぶりに30万枚を下回る「CD1枚で5人握手」も虚しく、ついにビジネスモデル破綻か
2024.07.24 芸能 -

吉岡里帆の美脚に大きなアザ…業界内からは「DV」を心配する声も
2024.07.08 芸能 -

“女版キムタク”の陰口も…田中みな実「何を演じても同じに見える」と業界内での評価イマイチ
2024.07.26 芸能 -

広末涼子「収入0円」でついに限界か 独立後の演技仕事0本、インスタグラムも不評で大ピンチ
2024.07.26 芸能 -

ドラマ『新宿野戦病院』都市伝説教の“チン患者”にお茶の間凍る…GP帯で下ネタ連発「正気なのか」「ギリギリでは?」
2024.07.26 芸能 -

中日OB会が「立浪監督続投」に待った! 星野派、落合派のチーム内派閥解消に向けて団結
2024.07.19 スポーツ -
『逃走中 THE MOVIE』爆死 全国で相次ぐ“ガラガラ報告”と酷評「最低オブザ最下位映画」「今年のワースト候補」
2024.07.23 エンタメ -
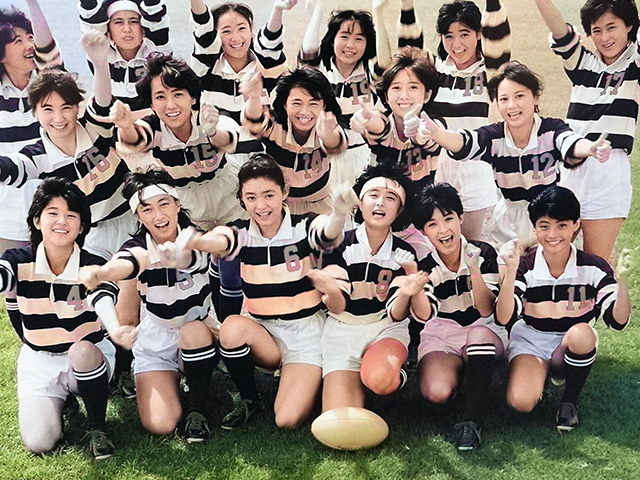
歌番組で1人だけモザイク処理!「映しちゃヤバイ人なのかな?」「一体何が…」
2022.05.09 芸能
合わせて読みたい
-

40歳・小倉優子“年内に3度目の結婚”の可能性!?「どんどんキレイになってる」若返りの裏側
2024.07.22 芸能 -

『Snow Man』メンバーで一番“演技下手”なのは…業界内で「期待ハズレ」とささやかれる演技力
2024.07.24 芸能 -
AKB48の新曲売上が15年ぶりに30万枚を下回る「CD1枚で5人握手」も虚しく、ついにビジネスモデル破綻か
2024.07.24 芸能 -

吉岡里帆の美脚に大きなアザ…業界内からは「DV」を心配する声も
2024.07.08 芸能 -

“女版キムタク”の陰口も…田中みな実「何を演じても同じに見える」と業界内での評価イマイチ
2024.07.26 芸能 -

広末涼子「収入0円」でついに限界か 独立後の演技仕事0本、インスタグラムも不評で大ピンチ
2024.07.26 芸能 -

ドラマ『新宿野戦病院』都市伝説教の“チン患者”にお茶の間凍る…GP帯で下ネタ連発「正気なのか」「ギリギリでは?」
2024.07.26 芸能 -

中日OB会が「立浪監督続投」に待った! 星野派、落合派のチーム内派閥解消に向けて団結
2024.07.19 スポーツ -
『逃走中 THE MOVIE』爆死 全国で相次ぐ“ガラガラ報告”と酷評「最低オブザ最下位映画」「今年のワースト候補」
2024.07.23 エンタメ -
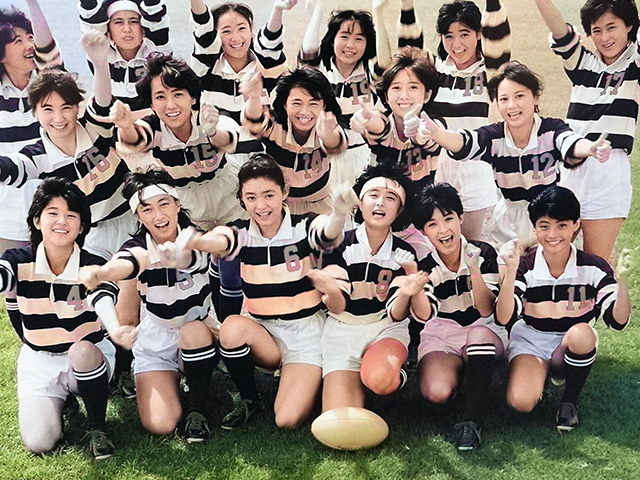
歌番組で1人だけモザイク処理!「映しちゃヤバイ人なのかな?」「一体何が…」
2022.05.09 芸能

