
短期集中連載『色街のいま』第3回「横浜・若葉町」~ノンフィクション作家・八木澤高明
昨年末、久しぶりにJR関内駅から伊勢佐木町を歩いた。以前は緊急事態宣言下ということもあり閑散としていて、街からは活気が失われていた。
【関連】短期集中連載『色街のいま』第2回「長野の某温泉街」~ノンフィクション作家・八木澤高明 ほか
肩がぶつかるほどではないが、通りは人で溢れていて、携帯電話ショップや雑貨屋は人で溢れていた。歩いた時期が年の瀬ということもあって、見違えるような活気だった。オミクロン株という厄介なウイルスの流行の兆しもあるが、街ゆく人々は緊急事態宣言が明けたことの喜びをそれぞれが噛み締めているように思えた。
通りを歩いていて目についたのは中国料理店で、店のほとんどは、中国人の経営者によるものだった。ここ数年、通りの空いたテナントには中国料理店の進出が目立つのだった。
この状況を見て、私はとある街のことを頭に思い出していた。「NK流」の名で有名になった、埼玉県の西川口である。中国料理店ばかりが軒を連ねて、どこか中国の街に紛れ込んだのかと錯覚するほど中国人で溢れた街になっていたのだ。
そして、コロナが流行する前には、中国人経営の風俗店やそこで働く風俗嬢も少なくなかった。
これから向かおうとしている若葉町周辺の立ちんぼたちが現れるエリアにも、中国人の娼婦が増えているのかもしれないと思った。
人で溢れた伊勢佐木町の通りを関内方面から右側に外れると、今回の目的地、若葉町がある。かつて500軒ものちょんの間があった黄金町とは大岡川を挟んで対岸にあって、ラブホテルが今も建ち並んでいる。ラブホテルの周辺に夜も更けると立ちんぼたちが姿を見せる。
私が、初めて若葉町を取材したのは、2000年代初頭のことだ。当時、黄金町のちょんの間が賑わう一方、若葉町にはタイ人やコロンビア人の立ちんぼたちが常時20人から30人はいて、妖しげな雰囲気を醸し出していた。
そもそも、若葉町が色街として産声を上げたのは、戦後のことだ。横浜に進駐した米軍は焼け野原に飛行場を建設し、周辺には米兵相手に春を売るパンパンたちが現れた。
今では駐車場となっているが、黒澤明監督の映画『天国と地獄』にも登場した「根岸家」という米兵や船乗り、娼婦たちが集う有名な酒場もあった。戦後76年が経ったが、若葉町の歴史は戦後の焦土から始まり今日に至るのだ。
時刻は午後9時半をまわった頃だろうか、若葉町の通りを歩いていくと、暗がりではなく、自動販売機の明かりの前に娼婦の姿があった。すらりとした足をした彼女は、ヒールを履いていることもあるだろうが、身長は180センチ近い。一見して最近、若葉町に多いニューハーフかと思ったが、話しかけてみると、その声音は女性で、中国人だった。
「新しいお客さんを見つけたい…」
年齢は20代前半だろうか。若葉町の娼婦は、暗がりに立っていることが多いが、明るい自販機の前に立っていたのは、自分の若さに自信を持つからだろう。代金を尋ねてみると、ホテル代込みで1万5000円と言った。ラブホテルではなく、近くに部屋があるので、そこに行くという。
この日、見かけた中国人の娼婦は彼女だけだったが、普段は5人ぐらいが体を売っていて、中国人が借りている部屋に連れ込んでいると教えてくれた。緊急事態宣言が明けてから、この町に来るようになったという。
彼女とは少しばかり話しただけだが、このままコロナが収まっていけば、連れ込み部屋を確保していることなど、組織的に動く中国人娼婦が増えていくことは間違いないと確信した。
私は昨年、緊急事態宣言が神奈川県に発出されていた時期にも若葉町を歩いているが、その時はブラジル人のニューハーフが目についただけだった。それが今回は、その時よりも国籍も人数も増えていた。ロシア、コロンビア、ブラジル、台湾、タイ、そして最初に話を聞いた中国人女性だ。
「前よりは忙しくなったけど、コロナ前のようになったわけじゃない。少しずつ、お客さんが戻ってきたような感じかな」
若葉町にある一軒のバーに足を運んだ。そこは立ちんぼたちが休憩に立ち寄る店で、ブラジル人のニューハーフが経営している。緊急事態宣言中、店は閑古鳥が鳴いていたが、この日は日本人の若者たちでいっぱいで、音程の外れたカラオケが店内に響き渡っていた。
若葉町で10年以上前から体を売っているニューハーフのブラジル人娼婦、エリーにも話を聞いた。
「コロナの前は体を売るだけじゃなくて、バーでもアルバイトをしていたんです。でもコロナが流行りだしてからは、感染したら怖いなと思って、ほとんど働かなかった。ブラジルでも大流行して、いっぱい人が死んだから怖くなったの。お客さんから会おう、会おうと言われたけど、頭がおかしいんじゃないかと思った」
昨年10月に緊急事態宣言が解除されてから、エリーは仕事に復帰した。
「若葉町には行くのはやめて、新大久保に行くことにした。新しいお客さんを見つけたいなと思ったの。コロナの時に会いたいなんて言う人の顔は見たくない」
新大久保での仕事は順調だという。
「休んでいた分、いっぱい働かないといけないからね。お客さんもコロナが怖いのか、エッチを何回もやろうと言わないし、キスしない人もいるから楽になった」
コロナの流行を経て、色街に生きる娼婦たちの状況は、確実に変化しているのだった。
八木澤高明(やぎさわ・たかあき) 神奈川県横浜市出身。写真週刊誌勤務を経てフリーに。『マオキッズ毛沢東のこどもたちを巡る旅』で第19回 小学館ノンフィクション大賞の優秀賞を受賞。著書多数。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -
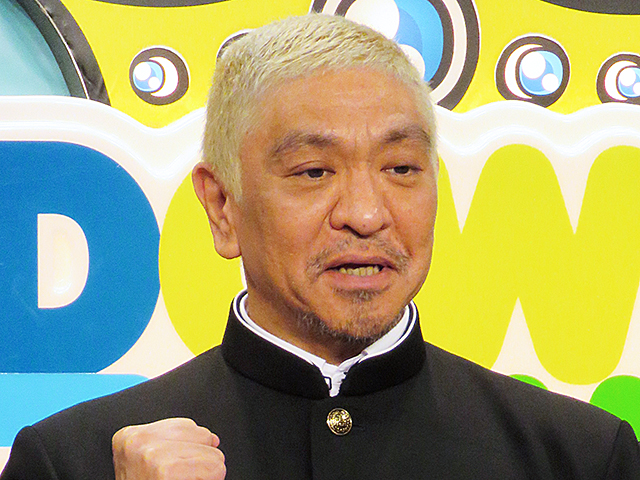
高須院長の「CM起用」バックアップで、2026年松本人志が地上波テレビに復帰の衝撃
2026.01.08 芸能 -
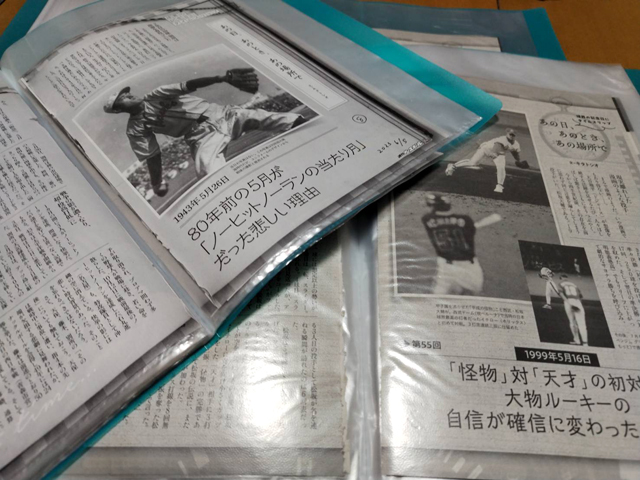
マリーンズ16年ぶり優勝が潰えた日に届いたDM――“野球考古学者”キタトシオは十数年の鬱憤を原稿へ叩きつけた
2025.05.10 スポーツ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

「結婚しないで歌手でいれば…」長渕剛に三行半を突き付けた石野真子の離婚の真相【週刊実話お宝記事発掘】
2024.10.31 芸能 -

やす子“善人キャラ”崩壊! 猪狩蒼弥への暴言で露呈した「裏の顔」に批判殺到
2026.01.07 芸能 -

園田競馬で大負けもご満悦! 十三ションベン横丁と梅田駅前ビル地下で体験した「なにわセンベロ旅」の極み
2026.01.08 エンタメ -

橋本環奈、深田恭子、あのちゃん…「メイド役が似合う芸能人ランキング」から編集部が夢見た“奇跡のメイド喫茶”最強メンバー
2026.01.08 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -
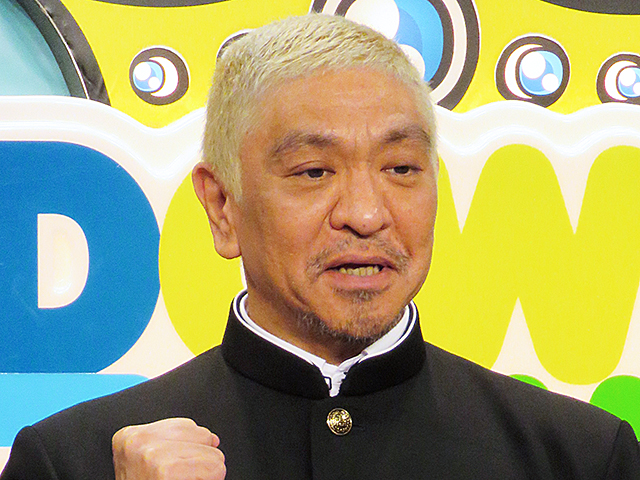
高須院長の「CM起用」バックアップで、2026年松本人志が地上波テレビに復帰の衝撃
2026.01.08 芸能 -
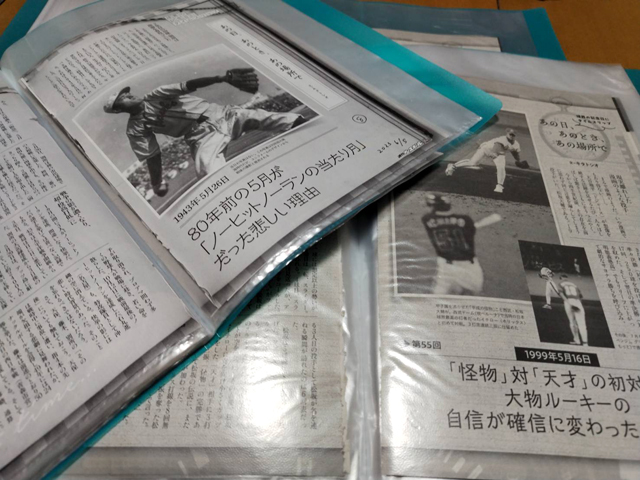
マリーンズ16年ぶり優勝が潰えた日に届いたDM――“野球考古学者”キタトシオは十数年の鬱憤を原稿へ叩きつけた
2025.05.10 スポーツ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

「結婚しないで歌手でいれば…」長渕剛に三行半を突き付けた石野真子の離婚の真相【週刊実話お宝記事発掘】
2024.10.31 芸能 -

やす子“善人キャラ”崩壊! 猪狩蒼弥への暴言で露呈した「裏の顔」に批判殺到
2026.01.07 芸能 -

園田競馬で大負けもご満悦! 十三ションベン横丁と梅田駅前ビル地下で体験した「なにわセンベロ旅」の極み
2026.01.08 エンタメ -

橋本環奈、深田恭子、あのちゃん…「メイド役が似合う芸能人ランキング」から編集部が夢見た“奇跡のメイド喫茶”最強メンバー
2026.01.08 芸能

