【難読漢字よもやま話】「魑魅魍魎」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.10.28
エンタメ
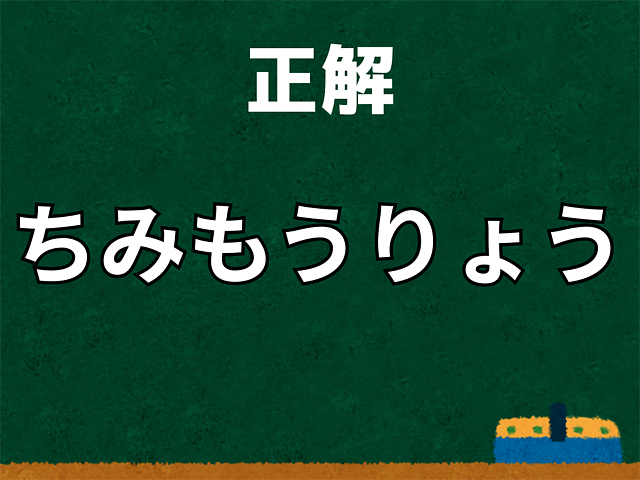
【漢字の由来と語源】
「魑魅魍魎(ちみもうりょう)」の語源は古代中国の歴史書である『春秋左氏伝(しゅんじゅうさしでん)』に由来し、悪い政治や乱世になると、こうした妖怪が現れて人々を惑わすという文脈で「魑魅魍魎」という表現が出てきます。
また、使われている漢字については「魑(ち)」が山岳地帯に棲む虎のような妖怪や精霊を、「魅(み)」が森や木々に潜む妖怪で、人を魅了したり惑わしたりする精霊を指し、「魍(もう)」が水辺や沼地に棲む妖怪で、人を欺く水の精霊を、「魎(りょう)」が土や大地に潜む妖怪で、土の精霊や地中の怪物を指すことからこの字が使われたと考えられます。
【魑魅魍魎に関するトリビア】
●特定の妖怪を指すわけではない
「河童」や「天狗」のように特定の名前を持つ妖怪を指すのではなく、さまざまな種類の得体の知れない化け物全般を指す「総称」です。
また、よく似たものに「鬼」がありますが、鬼が特定の強い悪霊や怪物を指すことが多いのに対し、「魑魅魍魎」はより多様で漠然とした「得体の知れない不気味な存在」全般を指す点で異なります。鬼も魑魅魍魎の一種とみなされることもありますが、概念の広さが違います。
●現代では比喩的な意味が主流
現在の日本語では、本来の妖怪の意味合いよりも、「悪事を企む得体の知れない者たち」や「権力争いの中に蠢く悪人」など、人間社会の悪しき存在を指す比喩として使われることが非常に多いです。
●道教や陰陽道との関連
中国の道教では、魑魅魍魎は人間を惑わす邪悪な存在とされ、さまざまな呪術や護符で鎮圧する方法が体系化されました。日本でも、平安時代の陰陽道において物の怪や怪異の総称として認識され、退治の対象となりました。
●魔除けの対象でもあった
古代の人々は、魑魅魍魎がもたらす災いを恐れ、桃の枝や鏡、特別な呪文などを用いて魔除けを行いました。これらは現代の厄除けの風習にも繋がっています。

- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能

