【難読漢字よもやま話】「窘める」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.10.27
エンタメ
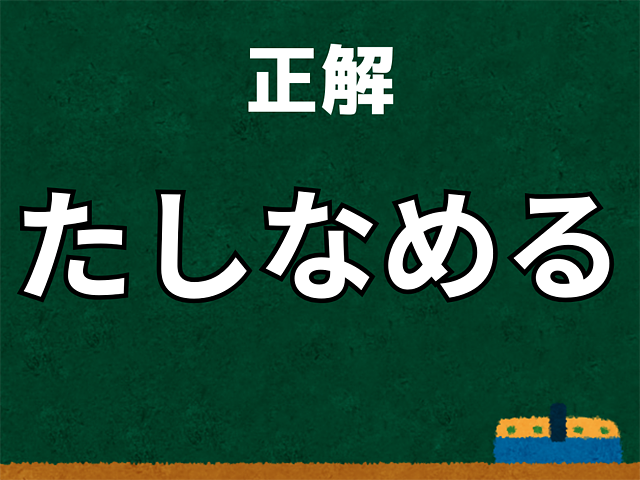
【漢字の由来と語源】
「窘める(たしなめる)」は良くない行いを注意してやめさせる、戒める、諫めるという意味ですが、言葉の語源は古語の「嗜む(たしなむ)」にあると考えられています。
というのも、この言葉は好んで行ったり、身につけていたり、趣味とするなどの意味がある一方、心掛けて行儀よくする、控えめにする、慎む、たしなみがあるなどの意味があり、それが他動詞形として「たしなめる」(人に慎むようにさせる、行儀よくさせる)という言葉になったと考えられているからです。
また、漢字の成り立ちについては、「窘」は「君(くん)」と「穴(あな)」の部首で構成されており、前者は締め付ける、まとめるという意味を持ち、後者は狭い場所、出口のない場所を意味します。
この二つが組み合わさることで、狭い場所に閉じ込められ、身動きが取れない状態、つまり「困り果てる」「窮する(きゅうする)」といった意味を表すようになったと考えられます。
【窘めるに関する豆知識】
●自己反省を促す言葉
相手を一方的に非難するのではなく、相手自身に間違いを気づかせ、自ら行動を改めることを期待する、という日本的なコミュニケーションスタイルを反映した言葉であると言えます。
●「叱る」「諫める」とのニュアンスの違い
「叱る」が感情的あるいは強く非を責めるニュアンスが強いのに対し、「窘める」は、相手の品位を損なわないよう、穏やかに、しかしきちんと間違いを指摘し、改めるよう促す、より理性的な忠告を指します。
また、「諫める(いさめる)」は主に目上の人や地位の高い人に対して、その非を指摘し、改めるように強く忠告する際に使われますが、「窘める」はそこまで格式張らず、目下の者や同僚に対しても使われる点で異なります。
●現代社会では行うにしても注意が必要
近年、パワハラをはじめとする各種ハラスメントが問題視されるようになり、窘め方にも配慮が必要とされるようになりました。相手の人格を否定するような言動は避け、建設的なコミュニケーションを心がけることが重要です。

- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能

