【難読漢字よもやま話】「杜撰」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.10.12
エンタメ
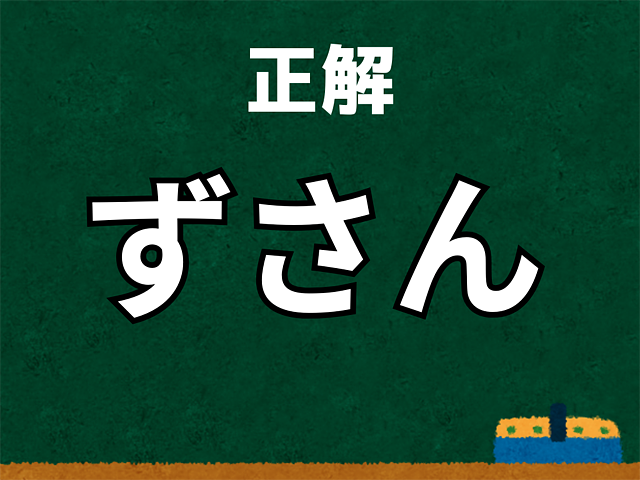
【漢字の由来と語源】
「杜撰(ずさん)」の語源は、中国の唐の時代の詩人、杜黙(ともく)という人物に由来します。杜黙は詩の才能はあったものの、規則や形式を無視していい加減で粗雑な詩を作ることが多かったとされています。そのため、人々は彼の詩を「杜撰(杜黙の撰)」と呼んで嘲笑しました。
これが転じて、「杜撰」は「いい加減で、粗雑なこと」という意味を持つようになったのです。
また、漢字の「杜」の字はそのまま「杜黙」の姓を表し、「撰」は「えらぶ」「つくる」という意味を持ちます。ここでは「杜黙が作った(詩)」という意味になります。
ちなみに、「杜」を「ず」、「撰」を「さん」と読むのは、中国から伝わった漢字の古い時代の読み方が定着したもののようです。
【杜撰に関する豆知識】
●杜黙は本当にダメ詩人だったのか?
語源となった杜黙は、実際にはそこまでひどい詩人ではなかったという説もあります。後世の批評家によってやや過小評価され、結果的に彼の名が「いい加減」の代名詞となってしまったのは、気の毒な話かもしれません。
●江戸時代にはすでに定着していた
江戸時代の辞書や文献にも「杜撰」の記述が見られ、この言葉がかなり古くから日本の言葉として定着し、使われていたことが分かります。昔も今も「いい加減なこと」は存在したのですね。
●「杜撰」は中国でも使われる言葉
「杜撰」は中国語においても使われ、意味もほぼ同じです。ただし、現代中国語ではやや古風または堅い表現と見なされることもあります。

- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相
2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”
2026.01.17 芸能 -
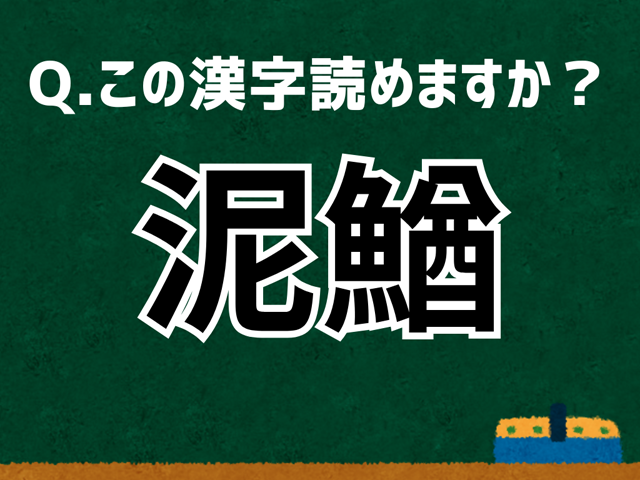
「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -
高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」
2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -
元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン
2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課
2026.01.18
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相
2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”
2026.01.17 芸能 -
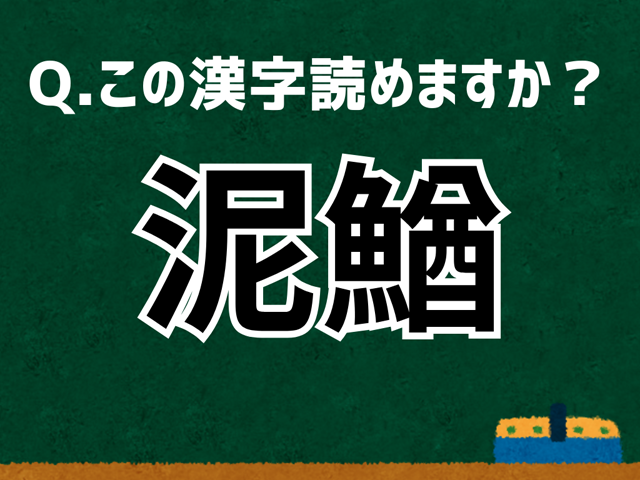
「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -
高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」
2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -
元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン
2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課
2026.01.18

