南海トラフ地震の発生時期に“5年前倒し論”求められる防災対策意識
2025.09.21

1月、国の地震調査委員会は南海トラフの30年以内の発生確率を「80%程度」に引き上げたが、一部専門家の間では5年以内に起きる可能性がある“前倒し論”も出始めている。
「退陣を渋ったとされる石破首相は、その理由の一つに『大地震』を挙げました。SNSなどでは『いつ起きるか分からない大地震を理由にするな』の批判が殺到した」(全国紙記者)
もっとも、前倒し論には根拠もある。
「南海トラフは駿河湾から日向灘にかけてのプレート境界を震源域として、過去に100~150年のスパンで発生してきたことから、次の推測は可能です。
また、ある専門官に言わせると、高知県室戸市の室津港の地震前後の地盤隆起の高さを調査することで、次にいつ起きるかほぼ想定できる説もあるほどです」(地震研究者)
【関連】トカラ列島群発地震で桜島大噴火、南海トラフ巨大地震が起こる可能性を専門家が指摘 ほか
地震調査委は「いつ起きてもおかしくない」
直近に起きた3回の南海トラフでいえば、1707年の宝永地震は地盤が約2メートル隆起。その次は約150年後の1854年の安政地震で、地盤の隆起は約1.2メートルだった。
そして、最後の昭和南海地震(1946年)は、約90年後だった。
「昭和南海の隆起は1.15メートル。これでいくと次の南海トラフは『2030年前後』という数字が弾き出されます。最近は“2025年から2030年の間が有力”と唱える人が増えつつあるのです」(同)
専門家の間でも、さまざまな論がある南海トラフ地震。ただ、地震調査委の平田直委員長は1月に「30年以内の発生確率80%程度」を公表した際、「80%とは、いつ起きてもおかしくない数字」と強調している。
我々は「防災対策」を急ぐしかない。
「週刊実話」10月2・9日号より
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

【歌姫降臨】中森明菜、20年ぶりツアーで「少女A」生歌解禁! “プラチナ席争奪戦”が勃発か
2026.02.17 芸能 -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念
2026.02.16 芸能 -
なぜ主力選手が次々と退団するのか? 蝶野正洋が語る新日本プロレスの契約“裏事情”
2026.02.17 -

【50代は注意!】「やりらふぃー」ファッション! 若作りが裏目に出る“痛おじ”の危ない共通点
2026.02.17 -

なかやまきんに君とケイン・コスギに確執 元マネージャー詐欺事件で友情パワーに亀裂か
2025.08.28 芸能 -
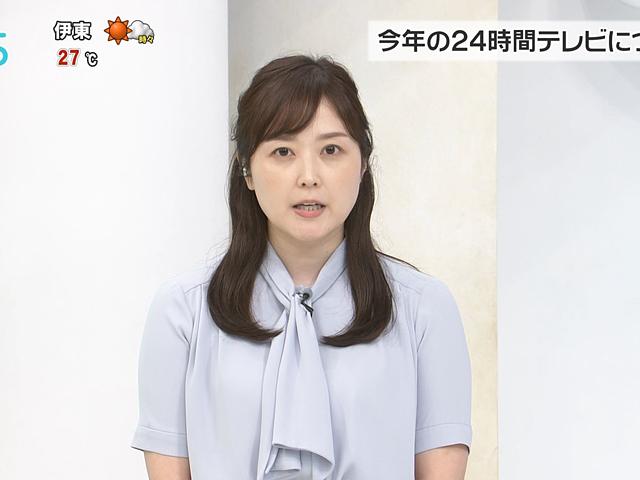
水卜麻美アナが部下12人を緊急招集! 日本テレビ17階で告げられた「重要事項」
2024.07.28 芸能 -

有村架純に“結婚”説!髙橋海人とのXデーは映画公開の6月か
2026.02.13 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -
高市早苗首相を襲う「健康不安説」
2026.02.16
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

【歌姫降臨】中森明菜、20年ぶりツアーで「少女A」生歌解禁! “プラチナ席争奪戦”が勃発か
2026.02.17 芸能 -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念
2026.02.16 芸能 -
なぜ主力選手が次々と退団するのか? 蝶野正洋が語る新日本プロレスの契約“裏事情”
2026.02.17 -

【50代は注意!】「やりらふぃー」ファッション! 若作りが裏目に出る“痛おじ”の危ない共通点
2026.02.17 -

なかやまきんに君とケイン・コスギに確執 元マネージャー詐欺事件で友情パワーに亀裂か
2025.08.28 芸能 -
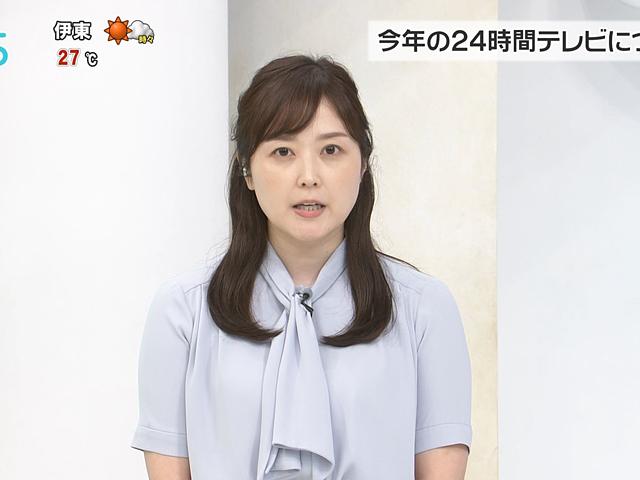
水卜麻美アナが部下12人を緊急招集! 日本テレビ17階で告げられた「重要事項」
2024.07.28 芸能 -

有村架純に“結婚”説!髙橋海人とのXデーは映画公開の6月か
2026.02.13 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -
高市早苗首相を襲う「健康不安説」
2026.02.16

