【難読漢字よもやま話】「齷齪」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.09.12
エンタメ
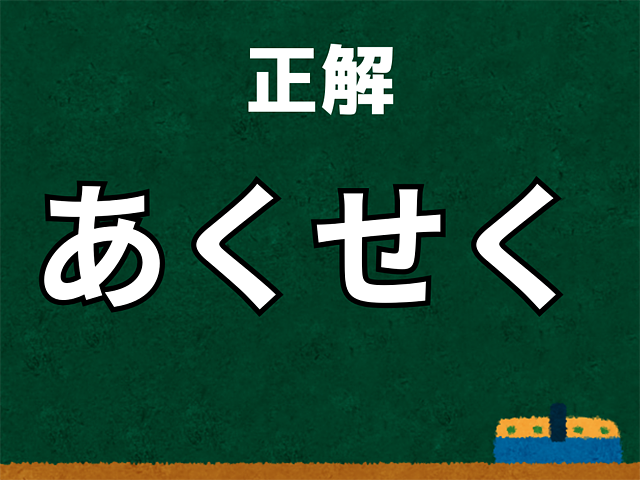
「齷」は歯がぎっしり並ぶ様、「齪」は歯がぶつかる音を表し、「細かいことにこだわりすぎる」という意味になりました。
「あくせく働く」が一般的ですが、実は平安時代から存在する古い言葉で、なんと『源氏物語』にも登場します。
【平安時代から使われていた「あくせく」】
あくせくという言葉は平安時代から使われていました。「『源氏物語』「若菜上」の巻に以下の記述があります。
「齷齪(あくせく)としたる人々の、さばかり仕うまつるを」(意訳:こせこせとした人々が、あれほどまでに取り仕切っているのを)
ここでは、宮廷行事の準備でせわしなく動く下役人たちの様子を描写しています。
この一節が登場する場面では、六条院の新年準備がテーマ。紫式部が当時の階級社会を反映した「立場による労働観」の違いを「貴族たちの優雅な振る舞い⇔下働きの者たちの「あくせく」した動き」という対比表現として使ったとみられています。
平安時代も現代も、「あくせく働く人」は組織の下層に集中。「忙しさの階級差」が存在、当時は身分、現代は役職で差が発生しています。
──1000年経っても変わらない「働く人の生態」。『源氏物語』を読むと、現代のオフィスと平安貴族社会が意外と似ていることに気付かされます。
- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能

