【難読漢字よもやま話】「煙管」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.09.11
エンタメ
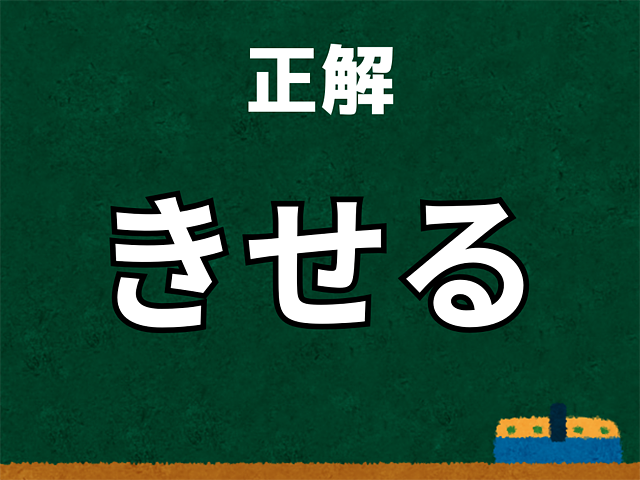
「煙」の「管」と書く組み合わせは、この道具の特徴をそのまま漢字に当てはめたもの。英語でも"kiseru"と日本語のままで通じるほど有名なアイテムです。
【きせるの歴史と特徴】
16世紀後半、ポルトガル人によってタバコと共に伝来。当初はタバコの茎をそのまま使った簡素なものでしたが、江戸時代には徳川家康愛用の銀製きせるなど高級工芸品として発展。庶民の間でも「印籠・刀・きせる」が町人の三種の神器と呼ばれるほど普及しました。

「キセル乗車」という言葉は、実は煙管(きせる)の形状に由来しています。
それは、煙管が「直線部分(羅宇)+曲がった部分(雁首)」で構成されるように、キセル乗車は「乗車区間(直線)+不正な乗り方(曲がった部分)」を表現。
また煙管で「一服」することが「息抜き」を意味したように、運賃をごまかす「息抜き行為」を「キセル」と表現した説もあります。
- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能

