ELLEGARDENがONE PIECE主題歌に 「俺たちのバンド」という幻想はどこへ消えたのか?
2025.08.06
エンタメ

彼らの多くは、かつての「インディーキッズ」、あるいは「インディー至上主義」に共鳴していた層だ。
一見するとその反応は、「国民的作品の主題歌なんてすごい!」「ELLEGARDENの新たな挑戦を応援したい」といった祝福に見える。
だが、その裏には複雑な感情が渦巻いている。
「孤独だった私に寄り添ってくれたエルレがワンピ主題歌だなんて」「GReeeeNと並べられるの無理」「紅白とか出ないでほしい」
こうした声に共通するのは、かつて“自分だけが知っていた”と感じていたバンドが、「みんなのもの」になっていくことへの違和感、そして、そこに生まれる自己のアイデンティティの揺らぎである。
ここにこそ、いまや過去のものとなりつつある「インディー=純粋」「メジャー=堕落」という構図の名残が見て取れる。
【関連】『ONE PIECE』1152話“回想の中の回想”が国内外で物議「インセプションかよ」 ほか
そもそもELLEGARDENとはなんだったのか?
かつて、インディーとは「売れないこと」や「知られていないこと」に価値を見出す倫理的な態度であり、商業主義に対抗する美学だった。
その中でELLEGARDENも、しばしば“インディー的想像力”の象徴として位置づけられていた。実際にはポスト・メジャー的存在であったにも関わらずだ。
ここで重要なのは、ファンがエルレに投影してきたカウンター的純粋性が、現実のバンド像よりも先行していたという点である。
そして今、想像の中にあった「俺たちのELLEGARDEN」が、国民的アニメ主題歌を手がける現実に直面したことで、かつてインディーを信じた人々の内側にある「自分が成長しても、バンドには変わってほしくない」という自己中心的な感情の残滓が露呈している。
だが、2020年代においては、メジャーとインディーの境界はすでに意味を失いつつある。
音楽ストリーミングサービス、YouTube、TikTok、アニメなどを経由した音楽体験の中で、インディー的表現とマス文化の接続はもはや例外ではなく、新たな常態である。
前の主題歌はGRe4N BOYZが担当
メジャーとインディーは対立するものではなく、むしろ共犯的に混ざり合うものへと変容してきた。
そんな中で、「GReeeeNと並ぶなんて」などという反応は、かつての対立軸にしがみつく中年特有のマイノリティ幻想のようにすら映る。
かつてのインディーが、時代と共に文化資本として制度化された今、「知ってる俺がえらい」的な優位性は、ただの時代錯誤だ。
むしろ、いま問われているのは 、変化する世界の中で、自分の倫理観や美学をどうアップデートするかという問題だろう。
エルレが変わったから裏切られたのではない。変わることに向き合わず、かつての構図にしがみつく自分自身が時代から取り残されているだけかもしれない。
合わせて読みたい
-

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

土屋太鳳のボディータッチにジャニオタ悲鳴!「触らないで!」イベントで絶叫
2022.01.26 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -

金正恩総書記への「娘のキス」全国放映 若者に広がる不満
2026.02.11 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
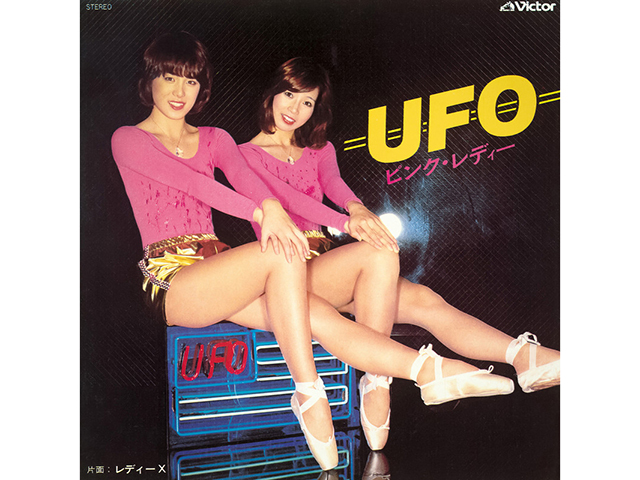
久米宏司会の音楽番組『ザ・ベストテン』伝説の初回1位! 歌謡界“黄金時代”の一翼を担ったピンク・レディー『UFO』
2026.02.11 エンタメ -

新宿・歌舞伎町「性風俗」の闇実態
2026.02.10 -
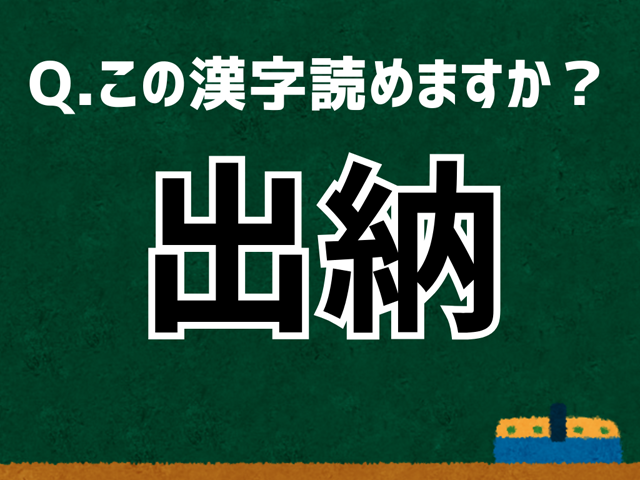
「出納」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.10 エンタメ
合わせて読みたい
-

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑
2025.06.14 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

土屋太鳳のボディータッチにジャニオタ悲鳴!「触らないで!」イベントで絶叫
2022.01.26 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆
2025.07.17 芸能 -

金正恩総書記への「娘のキス」全国放映 若者に広がる不満
2026.02.11 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
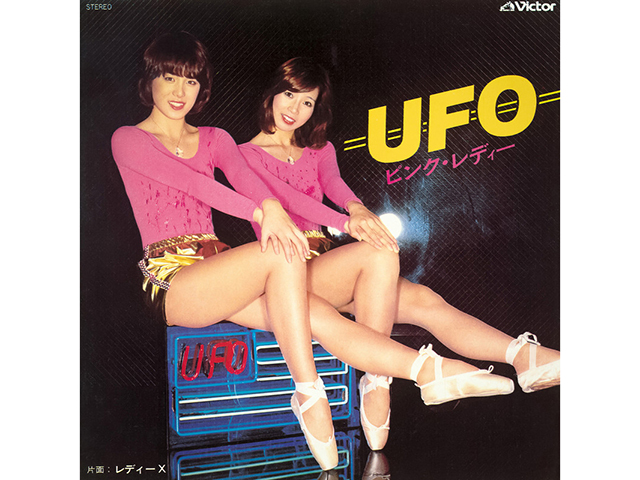
久米宏司会の音楽番組『ザ・ベストテン』伝説の初回1位! 歌謡界“黄金時代”の一翼を担ったピンク・レディー『UFO』
2026.02.11 エンタメ -

新宿・歌舞伎町「性風俗」の闇実態
2026.02.10 -
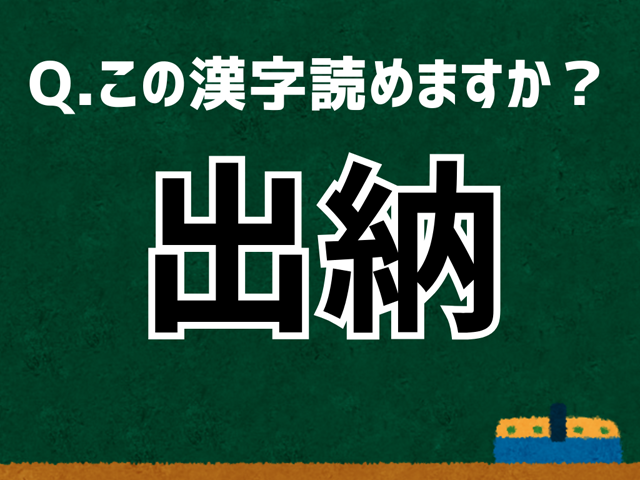
「出納」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.10 エンタメ

