【難読漢字よもやま話】「団扇」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.08.09
エンタメ
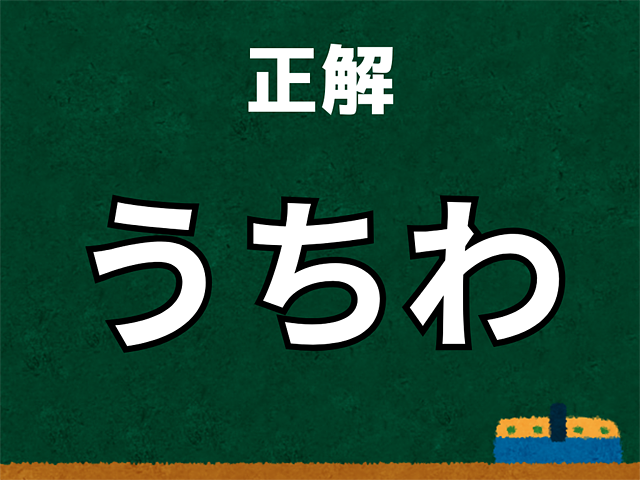.png)
この言葉も熟字訓(じゅくじくん)と呼ばれる特殊な読み方が使われていますが、「団(だん)」は、「丸」や「円」を意味し、「扇(せん)」は扇子の一種であることを表しています。
また、「うちわ」という読みの由来は、「虫を打ち払う羽(はね)」、つまり「打ち羽(うちは)」が転じて「うちわ」になったというものが有力です。また、顔や身を「打ち翳す(うちかざす)」から来ているという説もあります。
【うちわの歴史と現代での意外な用途】
うちわの起源は、古代中国にさかのぼります。日本では奈良時代から平安時代にかけて伝わったとされており、前述通りもともとは蚊やハエなどの虫を「打ち払う」ための道具として使われていました。
これが日本に伝わり、平安時代には貴族の間で用いられ、日差しや塵、または高貴な人が顔を隠すためにも使われました。さらに時を経て江戸時代になると庶民の間にも広がり、涼を取るための道具として広く使われるように。
今では夏祭りや盆踊り、花火大会、縁日など、夏のイベントに欠かせないアイテムとなっていますが、意外なのはアイドルのコンサート会場での利用法。応援メッセージや推しの名前を書き込んだ「手作りうちわ」を掲げて応援するファンが多く、定番の応援グッズとなっています。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”
2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影
2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”
2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相
2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -
後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”
2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”
2026.02.02 芸能

