「織田信長は本当に日本人らしくない」最期の言葉“是非に及ばず”に込められた覚悟を加来耕三が語る
2025.03.23
エンタメ
「さすがの信長も、じつは相当に疲れていたかと思います」

もちろん、もう少しで天下統一を果たし、さらには朝鮮半島、中国大陸まで征服するという、そんな壮大な計画もあったかもしれません。しかし、信長のようなタイプの人間は、きりがないわけです。
志半ばで明智光秀に殺され、信長には悔いが残っていそうですが、当人にしてみれば、ずっと全速力で走ってきたような人生です。さすがの信長も、じつは相当に疲れていたかと思いますね。
ひたすら走り続けるしかなく、きりがなかった信長は、もし本能寺の変で倒れなかったとしても、おそらく畳の上で死ぬことはなかったでしょう。
歴史には「反復性」がありますから、揺り戻しのように、時代が行きすぎれば元に戻ります。だから、信長が本能寺で死なず、いろいろなことをやったとしても、どこかで次代の、鎖国の世界へと戻ってくる。そういう考えもできます。
なぜかと言えば、古代、中世、近世、近代、現代という流れは、決して逆流しません。流れる方向は決まっている。違うスイッチが入って多少ズレたり、人物が入れ替わったりしても、例えば信長ではなく伊達政宗が何かをしたとしても、時代の流れそのものが逆流することはありません。
したがって「反復性」の原理で考えてみても、いくら信長が海外に覇権を広げたところで、どこかで収束しなければならなくなる。
江戸時代のように、鎖国の時代を迎えざるを得なかったでしょう。
きりがない生き方をしてきた信長は、自分を殺そうとしたのが光秀だと知ったとき、人生の最期に有名な「是非に及ばず」という言葉を残します。それを言った信長は、じつは安堵したんだ、と私は思いますね。
信長は危機に瀕しても常に冷静で、客観的で、本当に日本人らしくない。
だから憧れの対象にもなるのでしょうが、その部分を凝縮すると、自分の思うように「覚悟」を決めて生きた人間でした。
歴史を見てみると、やはり「覚悟」が揺らいだときに判断ミスをしたり、取り返しのつかない失敗をしている。われわれ現代に生きる者も、歴史から学べる“未来”は多いのではないでしょうか。

加来 耕三(かく こうぞう)
1958年、大阪市生まれ。奈良大学文学部史学科卒業。同大学文学部研究員を経て、現在は歴史家・作家として、独自の史観にもとづく著作活動を行う。 内外情勢調査会、地方行財政調査会、政経懇話会、中小企業大学校などの講師も務める一方、 テレビ、ラジオなどの番組監修・構成、企画、出演など多方面で活躍中。2023年に作家生活40周年を迎え、これまでに刊行した作品は400冊を超える。
- 1
- 2
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
ツッパリでも純愛でもない!?『北ウイング』が切り開いた中森明菜“アダルト路線”の衝撃
2026.01.17 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課
2026.01.18 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”
2026.01.17 芸能 -

球界関係者があ然! 現役引退・澤村拓一が描く「筋肉二刀流」のセカンドキャリア
2026.01.18 スポーツ -
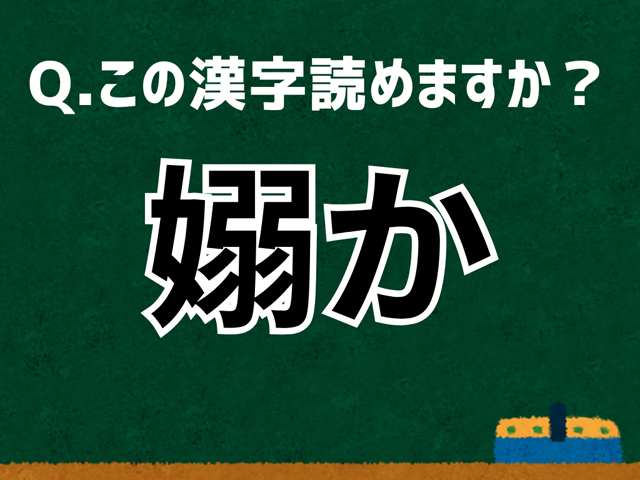
「嫋か」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.01.18 エンタメ -

和久田麻由子アナNHK退局で争奪戦!日テレ・テレ朝が「1億円」提示で白羽の矢
2026.01.18 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに
2026.01.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
ツッパリでも純愛でもない!?『北ウイング』が切り開いた中森明菜“アダルト路線”の衝撃
2026.01.17 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”
2026.01.14 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課
2026.01.18 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”
2026.01.17 芸能 -

球界関係者があ然! 現役引退・澤村拓一が描く「筋肉二刀流」のセカンドキャリア
2026.01.18 スポーツ -
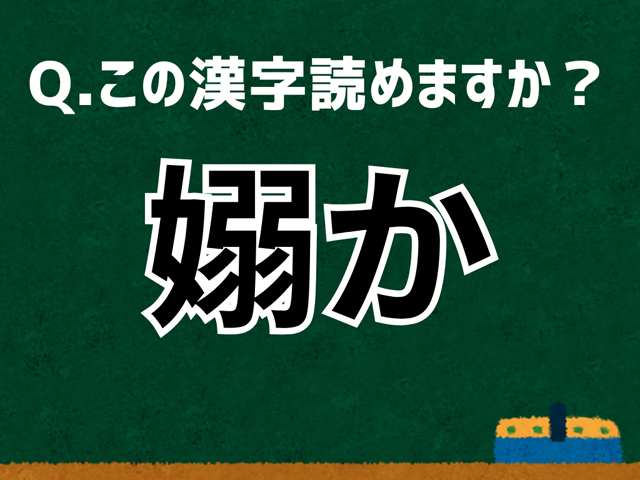
「嫋か」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】
2026.01.18 エンタメ -

和久田麻由子アナNHK退局で争奪戦!日テレ・テレ朝が「1億円」提示で白羽の矢
2026.01.18 芸能

