大谷翔平&真美子夫妻への取材がNGに!? 12億円新居“売却”なら日本メディア出禁の可能性
2024.07.18
スポーツ

日本テレビとフジテレビが行った大谷翔平選手への過剰な“自宅リポート”が、ますます大きな問題へと発展している。
両局は、大谷選手の新居の前からレポーターに中継させるなどして、住所がバレるような映像を放送。新居は観光地と化し、日本人観光客が訪れるようになってしまった。
【関連】大谷翔平オールスター大活躍で日テレ炎上 『24時間テレビ』制作発表との不運なタイミングで火に油「大谷に関わらないで」「絶対に募金しない」 ほか
これが大谷選手の逆鱗に触れ、両局は取材パスを凍結される事態となっていた。
「一部の米メディアによると、大谷選手は新居には住めないと話しているようです。日本でも『女性セブン』が、大谷選手が新居を売却する意向だと報じた。すでに住所は特定されていますし、今後も日本人観光客が訪れる可能性が高い。強盗などの心配もあるため、約12億円といわれる豪邸の売却は間違いナシでしょう」(スポーツ紙記者)
真美子夫人への取材申請が白紙に…
フジテレビは謝罪したものの騒動が収まる気配はないが、この件で一番激怒しているのが真美子夫人だという。
新居は新婚である2人が決めたもので、特に真美子夫人が立地や設備を気に入ったのだとか。
せっかく購入した新居を、テレビ局に晒されて手放さなければいけないとなれば、怒るのも当然だろう。
これをキッカケに真美子夫人が日本のマスコミに対して不信感を抱き、今後の取材に関してかなりの制約が出てしまいそうだと、民放関係者が話す。
「真美子夫人は日本代表レベルの元バスケ選手ということもあり、メディアへの露出が期待されていた。各テレビ局や新聞が、熱心に取材申請をしているところだが、この騒動ですべて白紙になりそうだ。それどころか、新居を売るような最悪の事態になれば、今後は日本メディアの取材に真美子夫人が答えてくれない可能性もある。他のメディアは、とんだトバッチリを受けた形です」
大谷夫妻がそろってテレビ出演すれば、とんでもない高視聴率を叩き出したことだろう。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

首都直下、南海トラフ…年末年始に警戒すべき巨大地震「全国警戒」
2025.12.26 -

「私、今も食べ盛りなんです(笑)」ソプラノ歌手の小野友葵子が語る美声の秘密
2025.12.21 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
昭和のヒット曲『アゲイン』は「吉田拓郎のメロディー、アグネス・チャンの超絶高音の兼ね合いが素晴らしい」
2025.12.23 エンタメ -

デュプランティエ獲得の裏で「SB-巨人-阪神」仁義なき巴戦
2025.12.26 スポーツ -

【難読漢字よもやま話】「坩堝」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.12.26 エンタメ -
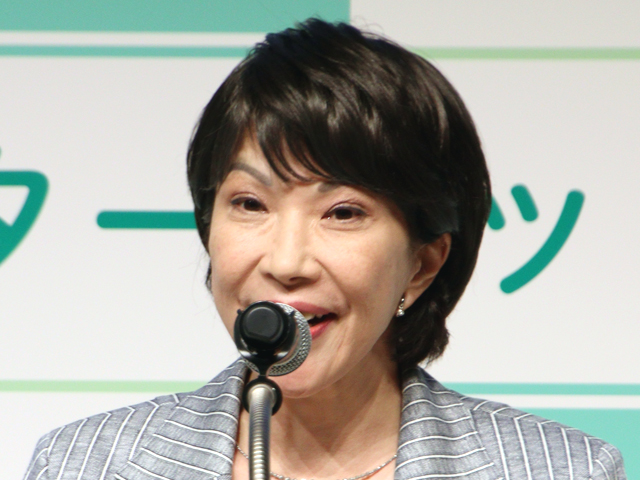
高市政権が断行する”影の被害者”救出に向けた「拉致事件解決戦略」は間に合うのか!?
2025.12.02 -
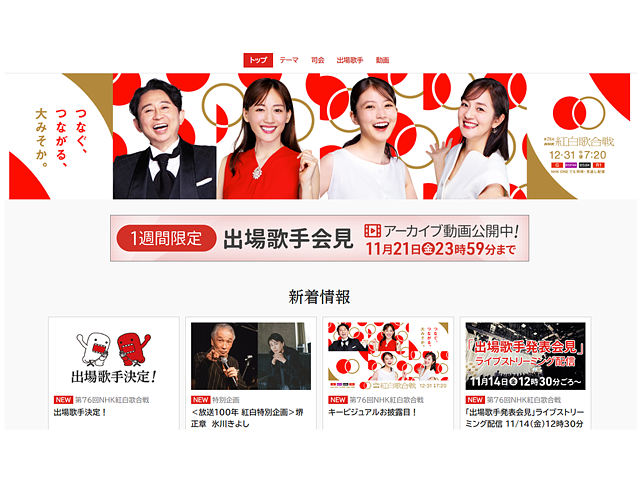
aespa紅白出場で「受信料拒否」の嵐!原爆揶揄騒動へのNHKの強行姿勢に国民が激怒
2025.12.24 芸能
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

首都直下、南海トラフ…年末年始に警戒すべき巨大地震「全国警戒」
2025.12.26 -

「私、今も食べ盛りなんです(笑)」ソプラノ歌手の小野友葵子が語る美声の秘密
2025.12.21 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -
昭和のヒット曲『アゲイン』は「吉田拓郎のメロディー、アグネス・チャンの超絶高音の兼ね合いが素晴らしい」
2025.12.23 エンタメ -

デュプランティエ獲得の裏で「SB-巨人-阪神」仁義なき巴戦
2025.12.26 スポーツ -

【難読漢字よもやま話】「坩堝」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.12.26 エンタメ -
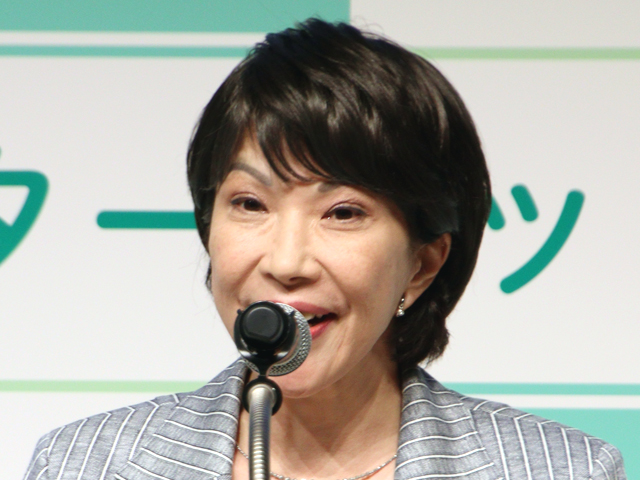
高市政権が断行する”影の被害者”救出に向けた「拉致事件解決戦略」は間に合うのか!?
2025.12.02 -
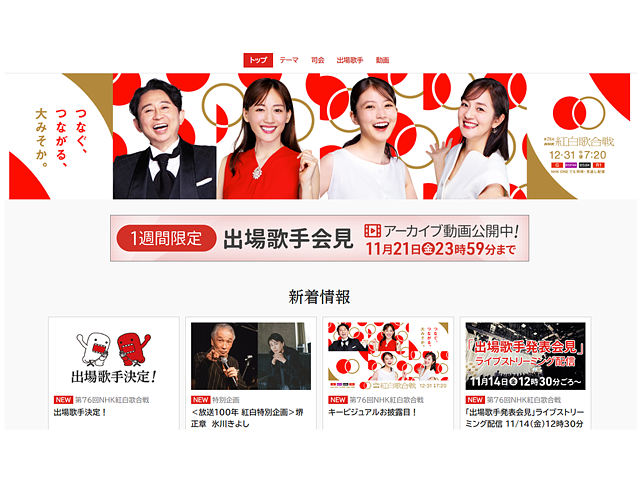
aespa紅白出場で「受信料拒否」の嵐!原爆揶揄騒動へのNHKの強行姿勢に国民が激怒
2025.12.24 芸能

