
小倉優子が早大受験を終えてリフレッシュ「E判定」から奇跡の“逆転合格”なるか
2023.02.25
芸能
2月19日に早稲田大学の受験を終えたばかりの小倉優子(39)が、2月21日に自身のインスタグラムを更新。美容院を訪れたことを報告し、ツヤツヤになったストレートの髪型を披露した。
この投稿をInstagramで見る
この前日には、1月26日以来の更新でSNSの再開を宣言。
【関連】“受験生”小倉優子インスタに法政大の赤本…「早稲田じゃなかったの?」と総ツッコミ ほか
「SNSを更新できていなかったのですが、今日からまた更新していきます 美肌アプリも始めました」とつづり、受験勉強から解放されたことを印象づけた。
この投稿をInstagramで見る
1月26日には、「風邪をひいてしまったり、目の前のやるべき事に追われながら余裕のない日々を過ごしていました この生活もあと少しです 残り一ヶ月切りました 不安なことを考えても点数は変わらないので何も考えずに残りの期間勉強します笑」とつづり、かなり自分を追い込んでいた。
芸能ライターが言う。
「すでに『100%!アピールちゃん』は放送が終了していますが、後継番組の『月曜の蛙、大海を知る。』が引き続き密着し、引くに引けなくなった。早稲田大学教育学部の偏差値は65から70ほどで、厳しい挑戦であることは間違いありませんが、法政大学なども受験しているのではないかとみられている。どこかに引っ掛かれば、特番などが組まれ、小倉にとって〝合格バブル〟到来となるのは間違いない」
鈴木福が偏差値40台の高校から「AO入試」で慶應義塾大学に合格し、物議を醸しているが、小倉は〝ガチ入試〟である。
早大の合格発表は3月1日。どんな結果でも、小倉の挑戦は評価されるはずだ。
合わせて読みたい
-

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -
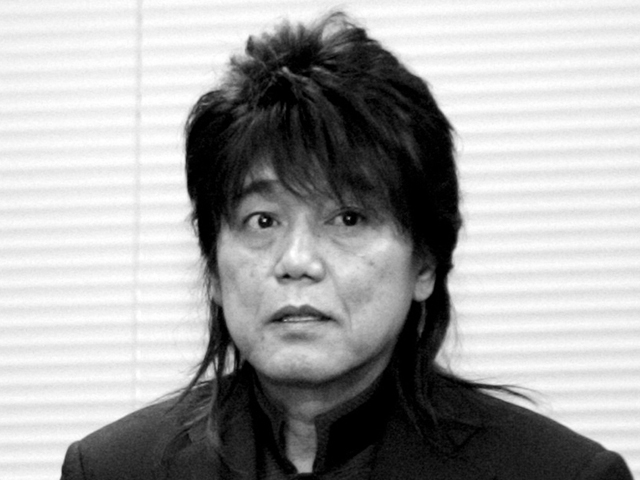
「俺とは恋人…いや夫婦だった」ジャニー喜多川氏の性加害を最初に告発したフォーリーブス・北公次の“恨み節”
2024.09.28 芸能 -

浜崎あゆみがついに「加工前」と「加工後」のビフォーアフター公開で業界騒然!
2023.02.28 芸能 -

浜崎あゆみ“激ヤセ”の裏事情を業界関係者が暴露!「中年太りを騒がれたのが相当ショックで…」
2024.10.29 芸能 -

「本当に不愉快以外何者でもない」「裏でそういうこと考えてるんだ」めざましキャスターの“後輩イジリ”が大炎上…
2024.10.29 芸能 -

阿部華也子『めざましどようび』クビ濃厚…10分キス報道から人気が下火 YouTube再生回数は全盛期の半分以下に
2024.01.06 芸能 -

『とんねるず』テレビ業界から声がかからない裏事情「番組を作りたいスタッフがほとんどいない」
2024.10.30 芸能 -

松田聖子&中森明菜の昭和歌謡が韓国で大ブーム! 1000億円規模の市場に
2024.10.14 芸能 -

趣里が父・水谷豊にそっくり!「右京さん憑依してたよね?」ドラマ『モンスター』のワンシーンが話題に
2024.10.30 芸能 -

多様性の風潮を悪用か エセトランス女性が脱毛エステに入会しセクハラ三昧!
2024.10.16
合わせて読みたい
-

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優
2024.10.09 芸能 -
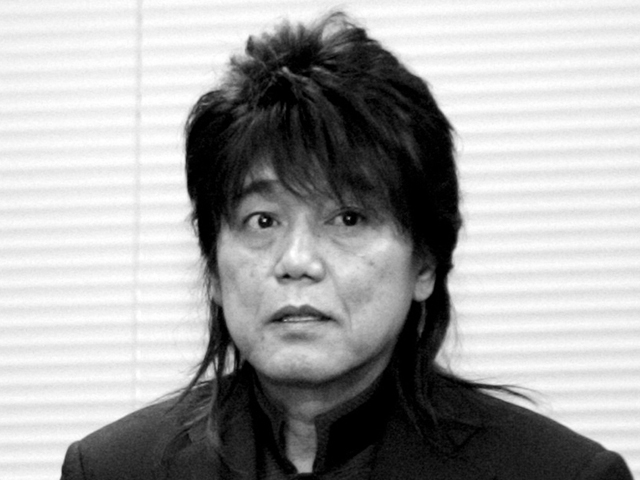
「俺とは恋人…いや夫婦だった」ジャニー喜多川氏の性加害を最初に告発したフォーリーブス・北公次の“恨み節”
2024.09.28 芸能 -

浜崎あゆみがついに「加工前」と「加工後」のビフォーアフター公開で業界騒然!
2023.02.28 芸能 -

浜崎あゆみ“激ヤセ”の裏事情を業界関係者が暴露!「中年太りを騒がれたのが相当ショックで…」
2024.10.29 芸能 -

「本当に不愉快以外何者でもない」「裏でそういうこと考えてるんだ」めざましキャスターの“後輩イジリ”が大炎上…
2024.10.29 芸能 -

阿部華也子『めざましどようび』クビ濃厚…10分キス報道から人気が下火 YouTube再生回数は全盛期の半分以下に
2024.01.06 芸能 -

『とんねるず』テレビ業界から声がかからない裏事情「番組を作りたいスタッフがほとんどいない」
2024.10.30 芸能 -

松田聖子&中森明菜の昭和歌謡が韓国で大ブーム! 1000億円規模の市場に
2024.10.14 芸能 -

趣里が父・水谷豊にそっくり!「右京さん憑依してたよね?」ドラマ『モンスター』のワンシーンが話題に
2024.10.30 芸能 -

多様性の風潮を悪用か エセトランス女性が脱毛エステに入会しセクハラ三昧!
2024.10.16

