
『性産業“裏”偉人伝』第24回/黄金町ちょんの間の女主人~ノンフィクションライター・八木澤高明
私が人を介して話を聞いた経営者は、黄金町界隈では「花のママ」と呼ばれていた女性だった。
終戦直後、黄金町の目の前を流れて横浜港へと注ぐ大岡川沿いの屋台に出入りしていた娼婦たちが体を売るようになり、その後、ちょんの間が形成されて、1980年代から2000年代初頭にかけて多くの男たちで賑わった。しかし、05年に一斉摘発に遭い、500軒あったというちょんの間は瞬く間に消えた。
【関連】『性産業“裏”偉人伝』第23回/色街のタクシードライバー~ノンフィクションライター・八木澤高明 ほか
私が黄金町を取材したのは00年前後のことで、そのとき働いていたのは、数人の日本人女性を除くとほとんどが外国人の娼婦ばかりだった。
花のママは1960年ごろから黄金町で店を始め、およそ半世紀にわたって街の生き死にを目に刻んだのだった。
取材当時、彼女の年齢は80代。彼女が冠する「花」とは、経営していたちょんの間の屋号である。
黄金町には売春だけでなく、麻薬が蔓延っていた時代がある。私が彼女に話を聞いたのは、かつて麻薬を売っていた店の後にできたバーだった。黄金町の生き字引に話を聞くには、ちょうどいい場所である。
ちょんの間経営からは手を引いていたが、依然、眼光は鋭く、金髪で、色街の主人というオーラを漂わせていた。喋り方も小気味良かった。
「いいときにはね、7軒の店をやってさ。月に4500万円は稼いだんだよ。そのお金で子供を育てたし、何も恥ずかしいことはしてないんだよ」
花のママは群馬の出身で、韓国人の父親と日本人の母親の間に生まれた。17歳のときに駆け落ちして横浜に流れてきたという。
「高校のときに、よく足利(栃木)にあったダンスホールに行ってね。当時はまだすらっとして、きれいだったから、目つけられたんだよ。今でいうナンパだね。家送っていくよなんて言われたときに、やっちゃったんだよ。当時は処女で、最初の男だった。それで結婚したいって親に言ったら猛反対されて、駆け落ちして横浜に出てきたんだ」
最初の男性は、横浜のヤクザだった。その繋がりで、大岡川沿いで屋台のおでん屋をやり始めた。
屋台を営むうちに、ちょんの間のママたちと知り合った。そこで、店をやらないかと誘われたのだった。
「ちょんの間を始めた頃は日本人の若いのもいたけれど、赤線が廃止されていたから、なかなか新しい女が入って来なくなっていたんだよ」
店をやりだして数年後、客足が鈍りだした。なんとか客を呼び込む方法はないかと思案していたが、なかなか妙案は思い浮かばなかった。
花のママは店を始めてから常に店の前で呼び込みをしていたが、雪の降る寒い日、2人の女が「仕事が欲しい」と声をかけてきた。2人は、モデルのような体形だったという。
「その場で、働きなよって言ったね。それが台湾人の女。若くてきれいだったから、すぐに客がついたね。客は、掃いて捨てるほど来たよ。もう来んなっていうぐらい」
収監先へ向かう途中、涙が…
そこから、黄金町で外国人の女性を置くという流れが出来上がった。すると、ママの店にヤクザが写真を持ってきて、「タイの女はどうだ」と売り込みに来るようにもなった。「写真を見たらきれいだったから、台湾の次に置いたのがタイ人だったのよ。最初のタイ人はヤクザに60万払って連れて来てもらったんだよ。それからは、女の伝手を使って集めるようにしたんだ。客を呼べたのは、タイ人だったね。チェンマイの女が一番良かった。タイでも北にあるから、肌も白いんだよ、体も小さくてね。日本の男って、見上げるような女のことは好きじゃないから、小さい女しか雇わなかったよ」
私たちが見た外国人娼婦がいた光景は、花のママがルーツだったのだ。
黄金町で商売をしていく中で、ヤクザとの付き合いも少なからずあった。
「それは、当たり前にあったよ。持ちつ持たれつだからね。これ預かってくれって言われて、カバンを渡されてね。中には拳銃が入っていたこともあったよ。みんな、命がけだったんだ」
売春という違法な商売をしている以上、逮捕されたこともあった。
「30年くらい前かな。その頃は7軒ちょんの間を持って派手にやっていたから、警察に目をつけられたんだ。最初にパクられたときは、署長さんがいい人だったから、調書だけでみんなを帰してくれたんだよ。それからはあんまり派手にやらないようにしてたんだけど、女も金が欲しいから、台湾人の女が昼間っから店を開けて客を取ってたんだ。それを刑事にパクられて、わたしゃ管理者ということで逮捕されたんだ」
裁判では4年の実刑判決を受けた。収監先は岐阜県の笠松刑務所だった。
「横浜から電車で岐阜に向かったんだけど、涙が知らないうちにこぼれてくるんだよ。あんなことは、後にも先にもあんときだけだね。子供を置いていくわけだろ。人生の先が見えないとは、あのときのことを言うんだろうね」
刑期を終え、彼女が戻った場所は黄金町だった。
「私にゃ、この街しか生きていく場所がなかったからね。この仕事をするしか、器量がなかったんだ」
その黄金町も、摘発で消えた。今の黄金町を見て、彼女が呟いた言葉が忘れられない。
「ただ街がきれいになっただけでさぁ。誰も飯が食えてねぇだろ。みんなが生きていけることを考えないといけねぇと思うな」
八木澤高明(やぎさわ・たかあき) 神奈川県横浜市出身。写真週刊誌勤務を経てフリーに。『マオキッズ毛沢東のこどもたちを巡る旅』で第19回 小学館ノンフィクション大賞の優秀賞を受賞。著書多数。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝
2024.10.20 芸能 -
.png)
侍ジャパン大谷限定ボトル投入の伊藤園が恐れる、高齢顧客の視聴離れの大誤算
2026.02.16 スポーツ -

小平奈緒が長野県でカフェをはじめたワケ “職場”の隣で恩返し
2025.08.21 スポーツ -
芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機
2026.02.12 芸能 -

鈴木保奈美 23年目の離婚は「人生奪還」の狼煙! 還暦前に放つ、眩しすぎる独り立ち
2026.02.15 芸能 -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり
2026.02.14 芸能 -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念
2026.02.16 芸能 -

石川佳純の“金メダル級”ボディに熱視線!綾瀬はるか猛追の現地レポ姿
2026.02.16 芸能 -
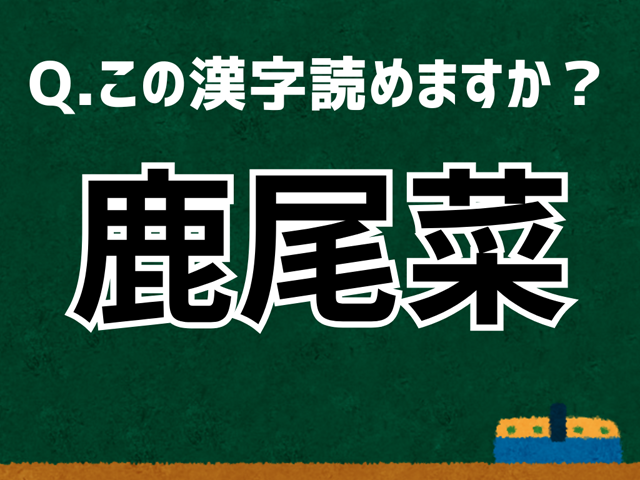
「鹿尾菜」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.15 エンタメ
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝
2024.10.20 芸能 -
.png)
侍ジャパン大谷限定ボトル投入の伊藤園が恐れる、高齢顧客の視聴離れの大誤算
2026.02.16 スポーツ -

小平奈緒が長野県でカフェをはじめたワケ “職場”の隣で恩返し
2025.08.21 スポーツ -
芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機
2026.02.12 芸能 -

鈴木保奈美 23年目の離婚は「人生奪還」の狼煙! 還暦前に放つ、眩しすぎる独り立ち
2026.02.15 芸能 -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり
2026.02.14 芸能 -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念
2026.02.16 芸能 -

石川佳純の“金メダル級”ボディに熱視線!綾瀬はるか猛追の現地レポ姿
2026.02.16 芸能 -
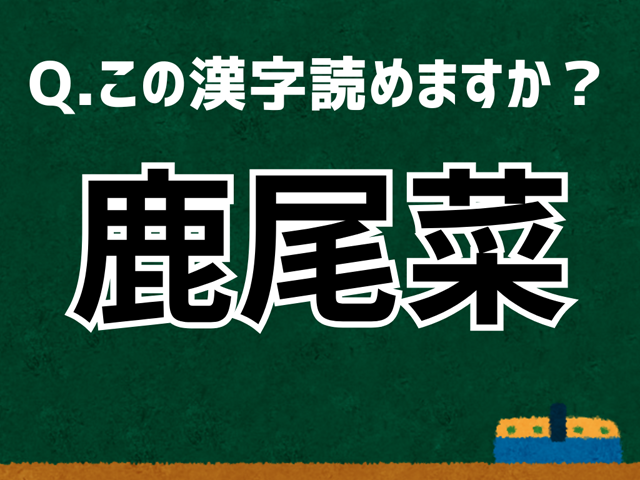
「鹿尾菜」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】
2026.02.15 エンタメ

