
『性産業“裏”偉人伝』第22回/外国人踊り子~ノンフィクションライター・八木澤高明
取材するうちに、劇場には「香盤表」というものがあり、その日に出演するストリッパーの名前が劇場の入り口やホームページなどに貼り出されていることに気付いた。さらに、いくつもの劇場を回っていくうちに、香盤表には決して名前が載らないストリッパーが存在することを知った。
今はなくなってしまったが、横浜に黄金劇場という劇場があった。その劇場を取材していると、香盤表には載っていない外国人ストリッパーがステージに立っていた。劇場のママにそのことを尋ねてみた。
【関連】『性産業“裏”偉人伝』第21回/売春島の元娼婦~ノンフィクションライター・八木澤高明 ほか
「警察の目につくから、外国人の踊り子さんは香盤表には載せないのよ」
劇場側も、外国人の踊り子を使っていると余計な疑いを持たれると自己規制して、あえて名前を伏せていたのだった。
ストリッパーはフィリピン人の女性だった。警察に配慮して、外国人の踊り子の名前を伏せていた理由について後から詳しく知った。
1990年代から2000年代初頭、日本各地のストリップ劇場では「本番まな板ショー」というものが行われていた。
今日の日本では考えられない、そんなショーが当時は行われていたのだった。そのショーの主役を担ったのが、多くのフィリピンや南米出身の外国人ストリッパーだった。
有名どころを挙げると、14億円を貢がせたことで話題となったチリ人のアニータも、まな板ショーを行っていた女性だ。
私が劇場を取材していた当時、警察の取り締まりなどにより、まな板ショーは行われなくなっていた。外国人ストリッパーが登場する劇場はいくつかあったが、そんななか、劇場内でストリッパーが体を売っている劇場が一つだけあった。
その劇場は長野県にあった。今はなくなってしまったが、外国人ストリッパーの写真や名前も堂々と貼り出している、まさに異色の劇場だった。
チケット売り場の横には、「ピンクサービス5000円」と書かれた紙が貼ってあって、フィリピン人の女性2人が客の相手をしていたのだった。その光景は、外国人のストリッパーが体を売り続けてきた歴史の最後の灯火だった。
劇場で体を売っていた女性の名前は、ナオミ。私は二度ほど彼女に話を聞いた。
当時、彼女は三つほどの劇場を回っていたが、体を売っていたのは長野のその劇場一つだけだった。
「まとまった期間呼んでくれるので、助かっているんですよ。体を売ることは嫌ですけどね」
ナオミは、まな板ショーが行われていた前の時代に来日し、全国の劇場を回っていたという。
ナオミは、踊りを披露するというより、体を売ることによって仕事を得ていたのだった。それが、全国的にまな板ショーが摘発されだし、彼女を呼ぶ劇場は激減した。ただ、長野のその劇場だけは、変わらず彼女を呼んでくれたのだった。
言ってみれば、長野の劇場は、変わらないスタイルで営業を続け、いつしか時代に取り残されていった場所でもあった。ナオミにとって、その劇場は日本で生きていくために必要な場所だった。
ピンクの個室で春を売る女
劇場で出番を待つ間、ナオミの楽しみは、フィリピンに暮らす息子とパソコン画面を通じてチャットをすることだった。「子供の成長だけが楽しみなんです」
フィリピンにいる息子は、まさか母親がストリップ劇場の楽屋からチャットをしているとは思っていない。さらに、まさか母親が体を売っているとは夢にも思っていないはずだった。17歳になる息子には、仕事はダンサーとだけ伝えてあったからだ。
マニラ生まれのナオミだが、父親は彼女が幼い頃に亡くなり、女手一つで育ててくれた母親も15歳のときに亡くしている。それからは、姉と一緒に親戚の家をたらい回しにされながら暮らしてきたという。
92年に初来日し、初めは静岡市内の工場で働いていたが、2000年代初頭からストリッパーになった。
「もともと踊ることが好きで、お酒も飲まないし、タバコも苦手。ホステスの仕事はできないから、この仕事を始めたんです」
ナオミは、フィリピンに暮らす息子と、姉夫婦とその子供のために、毎月10万円を送っていた。フィリピンの親族は、彼女の稼ぎに頼っていたのだった。もちろん、その親族も、彼女がどのようにその金を稼いでいるのか知らない。
ナオミのようなストリッパーだけでなく、売春をしていた外国人の女性たちは、家族のために体を売る女性たちがほとんどだった。
ナオミはステージをこなしつつ、内線で楽屋に連絡が入ると、ステージの横にある畳1畳分ほどの「小部屋」に向かう。そこが、彼女が体を売る場所だった。
そこは、豆電球が一つぶら下がっていて、並べられたビールケースの上にマットレスが置かれているだけの殺風景極まりない場所だった。部屋というより、物入れと言ったほうがしっくりくる。
その場所では、ナオミだけでなく、10年以上にわたって外国人のストリッパーたちが客を取り続けていた。殺風景な小部屋も、彼女たちにとっては、明日を夢見る宝の部屋だったのかもしれない。
八木澤高明(やぎさわ・たかあき) 神奈川県横浜市出身。写真週刊誌勤務を経てフリーに。『マオキッズ毛沢東のこどもたちを巡る旅』で第19回 小学館ノンフィクション大賞の優秀賞を受賞。著書多数。
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

甲子園途中辞退の広陵高校“秋季大会1回戦敗退”でセンバツ絶望的
2025.11.10 スポーツ -
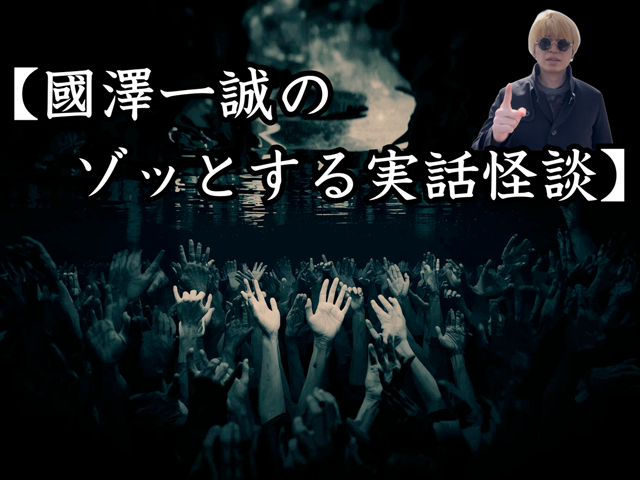
【國澤一誠のゾッとする実話怪談】第1夜 「覗くな」事故多発カーブミラーに映ったもう一つの世界
2025.12.24 エンタメ -

aespa紅白出場で「受信料拒否」の嵐!原爆揶揄騒動へのNHKの強行姿勢に国民が激怒
2025.12.24 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

内村光良の“舌禍”に再び批判 米津玄師トーク番組初出演で掘り返される「米津くんが喋った!?」事件
2024.08.27 芸能 -
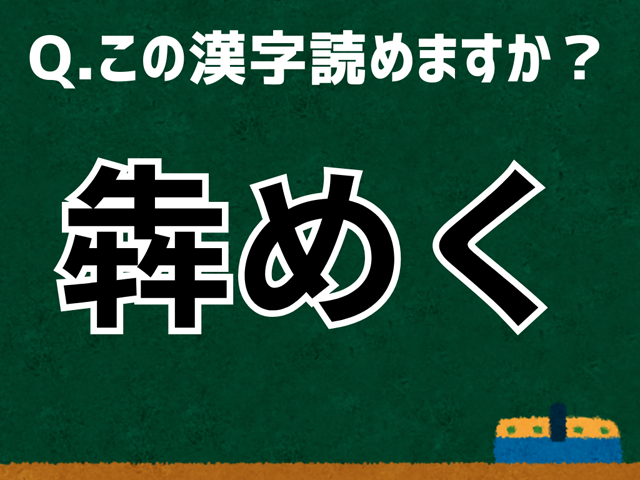
【難読漢字よもやま話】「犇めく」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.12.24 エンタメ -

高市政権が断行する”影の被害者”救出に向けた「拉致事件解決戦略」は間に合うのか!?
2025.12.02 -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ
2025.09.03 スポーツ
合わせて読みたい
-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】
2024.01.03 芸能 -

甲子園途中辞退の広陵高校“秋季大会1回戦敗退”でセンバツ絶望的
2025.11.10 スポーツ -
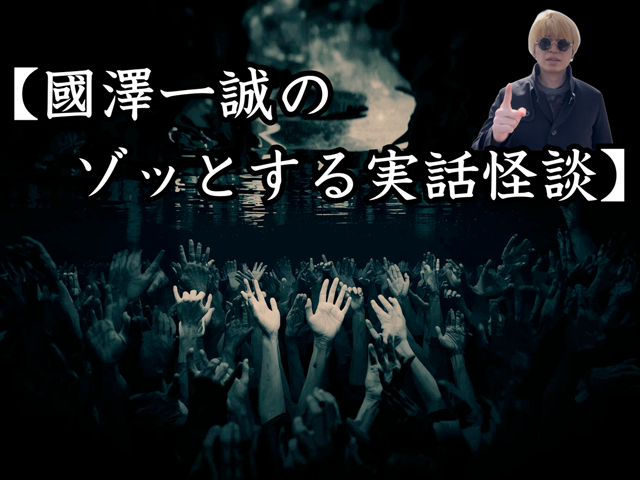
【國澤一誠のゾッとする実話怪談】第1夜 「覗くな」事故多発カーブミラーに映ったもう一つの世界
2025.12.24 エンタメ -

aespa紅白出場で「受信料拒否」の嵐!原爆揶揄騒動へのNHKの強行姿勢に国民が激怒
2025.12.24 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」
2025.07.30 芸能 -

内村光良の“舌禍”に再び批判 米津玄師トーク番組初出演で掘り返される「米津くんが喋った!?」事件
2024.08.27 芸能 -
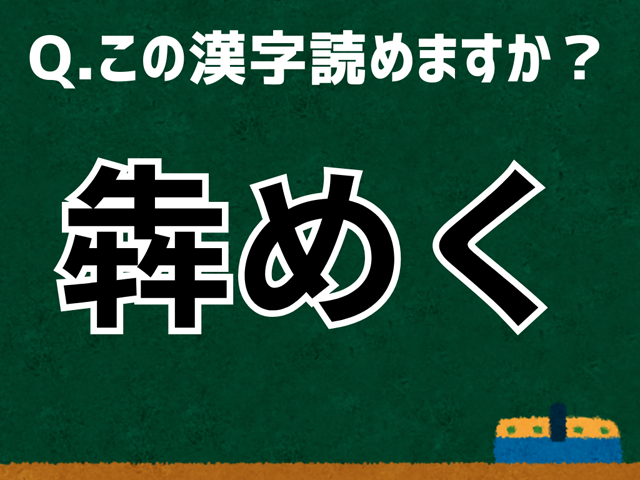
【難読漢字よもやま話】「犇めく」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識
2025.12.24 エンタメ -

高市政権が断行する”影の被害者”救出に向けた「拉致事件解決戦略」は間に合うのか!?
2025.12.02 -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ
2025.09.03 スポーツ

