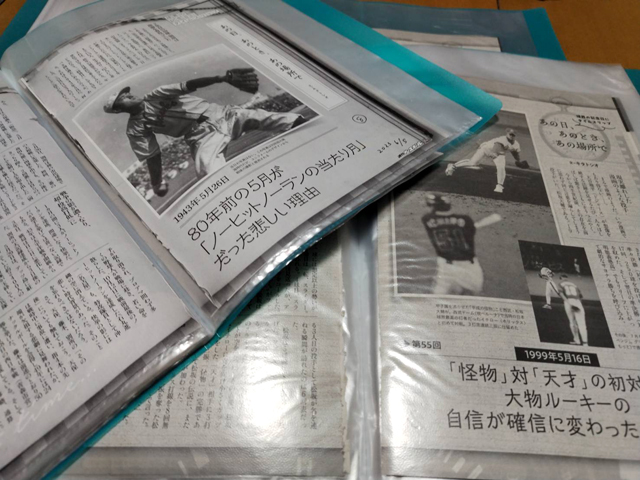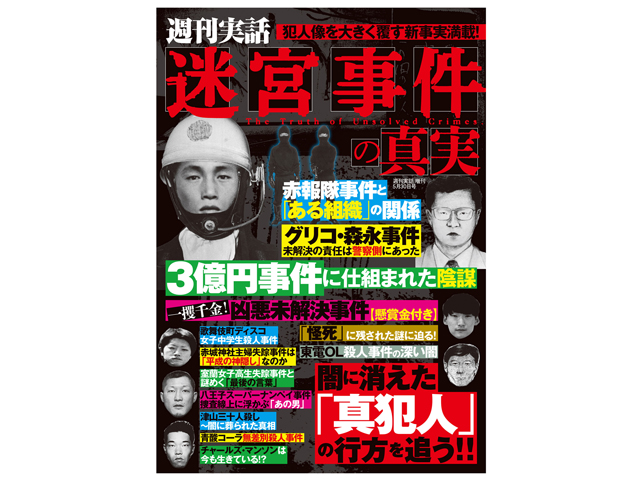新着ニュース
-

永野芽郁“不倫報道”の原因は今田美桜!? 芸能界きっての仲良しコンビ崩壊か
2025.05.11 芸能 -
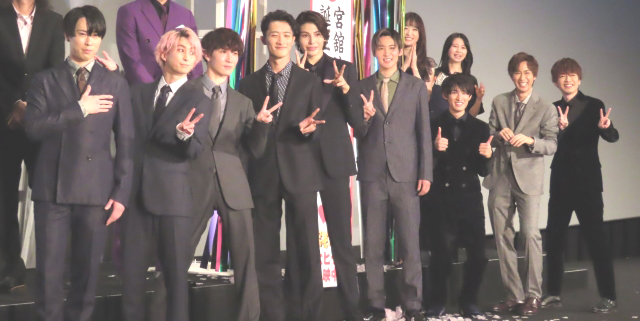
嵐の活動再開でSnow Man人気に陰り?(旧)ジャニーズ世代交代の捻じれと未来
2025.05.11 芸能 -

蝶野正洋「ベイスターズ一筋って正直…飽きない?」 DeNA三浦監督にブッ込み質問連発!
2025.05.11 スポーツ -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?
2025.05.11 芸能 -

“イチロー議員”が狙う甲子園大会の「1校の格差」是正
2025.05.11 スポーツ -

“玉木首相”の隠し玉 国民民主が参院選にイチロー氏を擁立へ
2025.05.11 スポーツ -

“医療現場の闇”男性医療従事者による女性患者への胸クソわいせつ事件4例
2025.05.10 -

今期の覇権ドラマは『続・続・最後から二番目の恋』なのか?
2025.05.10 エンタメ